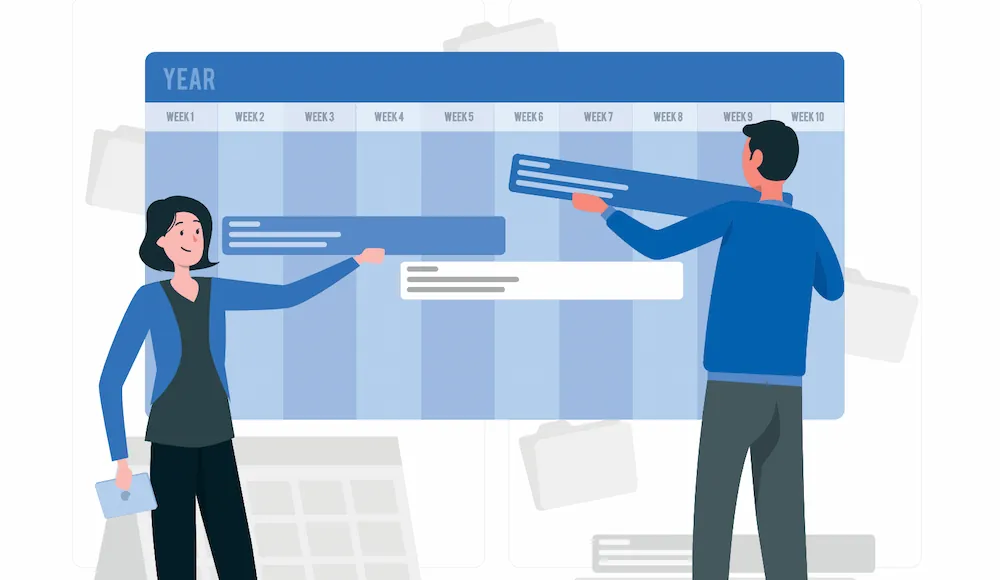会社の評価制度
人事評価制度の導入や既存の人事評価制度を大幅刷新するのは、非常に時間と労力のかかる仕事です。
人事担当者としては、制度を無事ローンチできた時点で肩の荷が下りる気持ちになりますが、その制度が本当に意味を持つのは、その後の「運用フェーズ」です。
どんなに緻密に設計された制度でも、実際に現場で活かされなければ効果を発揮できません。
今週のブログでは、人事評価制度を継続的にチューニングし、熟成させていくための考え方をお伝えします。
目次
人事評価制度導入後に見えてくる課題

人事評価制度をスタートさせると、さまざまな問題が見えてきます。
よくある課題とその対策について詳しく見ていきましょう。
目標設定の難しさ
目標管理(MBO)を導入している企業では、
「無難で達成しやすい目標を設定する」
「前年の目標をそのまま使いまわす」
「目標が曖昧なため期末に評価しようにも評価できない」
といったケースが見られます。
このような目標設定では、「チャレンジ促進」や「成長促進」といった制度本来の目的が果たされにくくなります。
![]() 目標設定の質を高めるための仕組みづくりが重要です。
目標設定の質を高めるための仕組みづくりが重要です。
具体的には
- 目標の立て方の研修を実施する
- 部門目標を明確にし、それに基づいて個人目標を立てるプロセスを徹底する
- 目標に具体的な数値や期限を盛り込む
- 目標設定の段階で上司と部下でじっくり摺り合わせするなど、手間をかける
などが有効です。
評価のばらつき
評価基準を整備していても、実際の現場では評価者によって評価の甘辛が異なることがあります。
![]() 「上司Aさんは厳しすぎる」
「上司Aさんは厳しすぎる」![]() 「X部の評価は全体的に甘すぎる」
「X部の評価は全体的に甘すぎる」
こういった不公平感が、社員の納得感を損なう要因となります。
![]() 評価者毎の評価傾向を分析し、極端に「甘い/辛い」が見られる評価者には評価の見直しをしてもらうことで、一定程度平準化が可能です。
評価者毎の評価傾向を分析し、極端に「甘い/辛い」が見られる評価者には評価の見直しをしてもらうことで、一定程度平準化が可能です。
また、評価会議等の場で各部門責任者が一堂に会し、個々の社員の評価について目線合わせを行うのも有効です。

評価項目が実態とずれている
制度設計時に作成した評価項目が、現場の仕事内容や能力判断要素と乖離してしまうこともあります。
事業環境の変化や職種の多様化が進む中、評価項目を見直す必要があるケースも多々あります。
![]() 評価シートに書かれた評価項目を一部見直したり、新たな評価項目を付け加えるなどで調整可能です。
評価シートに書かれた評価項目を一部見直したり、新たな評価項目を付け加えるなどで調整可能です。
評価結果が肌感覚と合わない
評価制度にもとづいて評価を実施すると、その結果が最終的には数値としてデジタルに出てきます。
その数値が、従前の評価の仕方と比べて高い精度の評価につながる場合と、逆に本来評価が高く出るべき人が平均的な結果になってしまうなど、肌感覚の評価と乖離が生じる場合があります。
どちらであれ、このズレを放置すると評価の妥当性や社員の納得度を損なうことになります。
![]() 例えば、目標管理(MBO)と行動評価の2つで評価を行っている場合、最終的な評価結果を算出するための両者の評価割合を調整することでズレを埋められることがあります。
例えば、目標管理(MBO)と行動評価の2つで評価を行っている場合、最終的な評価結果を算出するための両者の評価割合を調整することでズレを埋められることがあります。
MBOの達成度も大事ですが、そこにいたる行動をしっかり評価したい考えであれば「MBO評価:行動評価」の割合において行動評価の比率を少し高めてみる、などの工夫をします。
また、評価づけを5段階で行っていると、迷った時に真ん中の3を選ぶ傾向があり、本来は差がある2人の部下に対して同じ評価をつけてしまう可能性があります。
この場合、評価を6段階にすることでメリハリをつけやすくなります。
職種によって評価傾向が異なる場合も
職種によって何を評価すべきかが異なるので、その違いに制度を適応させる必要もあります。
例えば営業職であれば、数字成果をより高い割合で評価に組み込んだ方が納得感のある結果が出やすいです。
一方で、総務のようなその時々で臨機応変に多様な業務を行う職種は、仕事への取組み姿勢、主体的な行動、気の利いた対応などが評価されるべきでしょう。
いずれにしても、最終評価結果を導き出すロジックを確認し、どこに乖離や不整合が出ているかを検証することで対応策を打てます。
なお、直接評価項目には入っていない事象(ex. 遅刻欠勤、賞罰、本来業務外のプラスαの活動など)を考慮して評価結果を最終調整することも考慮が必要です。
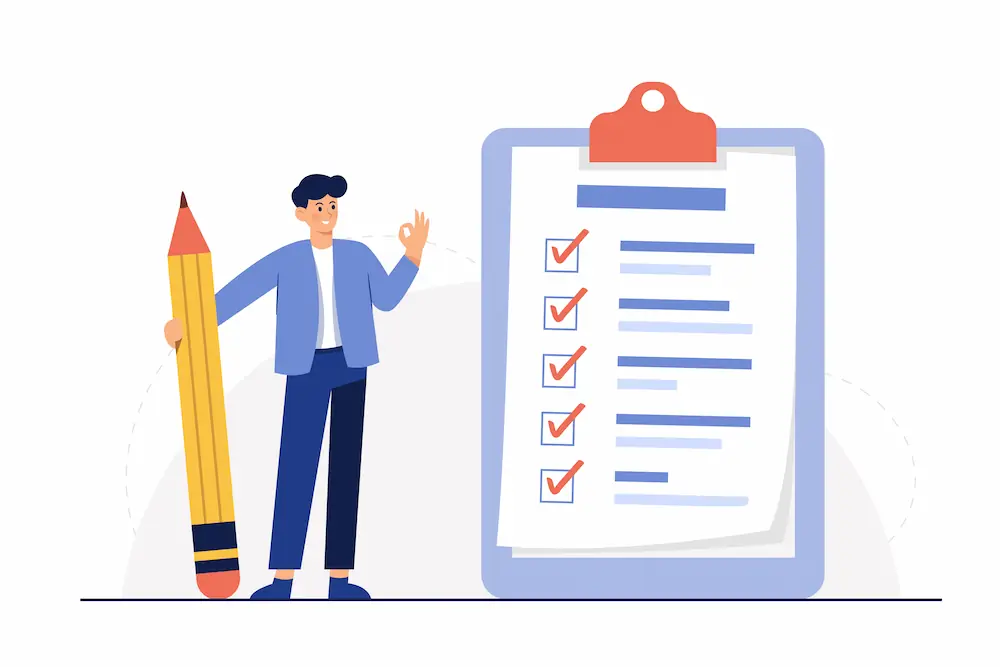
等級が実際の能力に見合っていない
等級制度を組み込んでいる場合、制度導入時に各社員をいずれかの等級に所属させます。
しかし実際に評価制度をスタートしてから「BさんはCさんより上の等級に所属しているのに仕事ではCさんの方が優秀」といった事実が露呈します。
少しの差であれば、段階的に是正可能ですが、ギャップが大きい場合には何らかの対応が必要になります。
新たに人事評価制度を入れる会社では、制度導入段階では社員の能力を客観的に示す材料がないため、とりあえず仮で所属等級を決めざるを得ない場合があります。
そのため、上記のような逆転現象が起こりがちです。
逆転現象が多数発生したまま放置すると、制度自体の信頼性が損なわれるリスクがあります。
![]() 制度導入から1年後や2年後の節目に、改めて正式な所属等級を見直し、並べ直すことが必要です。
制度導入から1年後や2年後の節目に、改めて正式な所属等級を見直し、並べ直すことが必要です。
報酬水準が市場とずれている
現在のように毎年ベースアップして初任給を大幅に上げる会社が増えている環境下では、評価制度導入時に設定した給与水準が、数年後には競合の水準に明らかに劣後することもありえます。
![]() 自社の報酬水準が競争力を維持しているかどうかを定期的に検証し、必要に応じて見直す必要があります。
自社の報酬水準が競争力を維持しているかどうかを定期的に検証し、必要に応じて見直す必要があります。
毎年の継続的なチューニングが制度を育てる
人事評価制度は、導入して終わりではありません。
環境の変化や現場の実態との乖離に対して、毎年細やかなチューニングが求められます。
よって、制度開始時点で100点である必要はなく、70~80点程度の状態でスタートし、毎年段階的に熟成させながら100点に近づけていくのが現実的なアプローチです。
チューニングする上では、前の段落でお伝えしたような諸問題を浮き彫りにする必要があります。
そのために、次のような調査・ヒアリング等が有効です。
現場の声を聞き、制度の健全性を確認する
制度の改善には、現場からのフィードバックが欠かせません。
以下のような視点でヒアリングを行うと効果的です。
![]() 評価者からヒアリング
評価者からヒアリング
評価のしやすさ・分かりやすさ、評価者の負荷、目標設定の仕方と評価、評価結果のフィードバックの仕方、部下の行動の変化など
![]() 被評価者からヒアリング
被評価者からヒアリング
評価の納得感、制度の理解、自分の成長に制度がプラスになっているか、改善してほしい点など
![]() 経営陣からヒアリング
経営陣からヒアリング
会社の方針や戦略と制度の整合性が取れているか、評価すべき人が適切に評価されているか、制度が人材力の向上につながっているかなど
昇給率や報酬水準を客観的に検証する
次のような観点で、数値面からも制度の適正さを検証しましょう。
- 昇給率が他社(同業種、競合企業、同等規模の企業等)の昇給率と比べて適正か?
- 昇給に伴い自社の人件費は適切にコントロールされているか?
- 生産性や労働分配率は適正なレンジか?
また、新卒就活生や中途採用の求職者から見たときの自社の報酬水準や魅力も確認し、採用競争力が落ちていないかをチェックすることも大切です。
まとめ
人事評価制度は一度作って終わりではありません。
「完璧な制度を最初から作る」のではなく「育てながら磨いていく」姿勢、そして運用と改善プロセスの積み重ねが何よりも重要です。
導入後に現れる課題をひとつひとつ拾い上げ、毎年小さな見直しや調整を重ねることで、制度が実態にフィットし、組織文化に根づいていきます。
人事部門だけで抱え込まず、現場の声や経営の視点を取り入れながら、制度を組織全体で育てていくことが、社員の納得感と組織力の向上につながっていくでしょう。
こちらの記事もおすすめです。