人事の仕事
人事とは「二律背反」の視点を同時に持つことが求められる仕事です。
例えば「社員のために給料を上げてあげたい」
という考えと
「利益確保のために人件費を抑制したい」
という考えの双方を持っている必要があるということです。
両者には絶対の正解はありません。状況に応じて解が異なるからです。
業績が悪化して利益確保がままならない状況であれば人件費を抑えざるを得ないし、
業績がよく生産性が上がっているならば給料を上げていくべきです。
最近よく話題になる「リモートワークを認める会社」と「認めない会社」議論も同様です。
社員が通勤せずに効率よく働けるリモートワークを重視する会社もあれば、コミュニケーションやアイディア創発を重視して出勤を命じる会社もあります。
単純にどちらが良い悪いとか、自分自身がどうしたいかではなく、その会社の置かれた状況を踏まえ、会社の成長のために何が最適かを判断しなければなりません。
人事の仕事の難しさは、絶対的な答えのない二律背反の間を行ったり来たりしながら、どの辺りに意思決定の軸を置くべきかを考え抜くところにあります。
人事の中にはたまに「自分の思想・信条に偏ってしまう人」がいますが、人事は思想ではなく経営そのもの。
会社の成長に向けて人・組織をいかに最適化するかを考える仕事です。
今週のブログでは、人事が抑えておくべき二律背反の視点についてお伝えします。
目次
給料が高い高収益企業 VS 給料が低い高収益企業

高収益企業の中には、社員の平均給料が非常に高い会社もあれば、低い会社もあります。
前者は
![]() 「優秀な人材に個の能力を存分に発揮してもらい、仕事のクオリティを高め、高い収益を生み出す」モデル。
「優秀な人材に個の能力を存分に発揮してもらい、仕事のクオリティを高め、高い収益を生み出す」モデル。
一方で後者は
![]() 「できるだけ標準化され仕組みが整った仕事を担当させ、平均的な人材でも効率よく稼ぐ」モデル。
「できるだけ標準化され仕組みが整った仕事を担当させ、平均的な人材でも効率よく稼ぐ」モデル。
個人の能力に依存することなく、誰がやっても一定の結果が出るような仕組みを作り上げているので高収益を実現しています。
さて、この両者において、あなたはどちらが望ましいと思いますか?
ご察しの通り、両者に優劣をつけることはできません。
高収益企業ということは、お客様に価値をもたらしていることの証であり、いずれも存在価値のある会社ではないでしょうか。
人事方針として、優秀な人材に高い給与を出すモデルか、平均的な人材に低い給与のモデル化か、どちらを選択するかは、経営の考え方次第です。
人によっては「低い給料で社員を働かせて儲かっている会社は好きじゃない」という人もいるでしょう。
しかし、人事の仕事に携わる人は、そのような思想や感情を抑制できなければなりません。
今現在、高い給料で高収益の企業であっても、その社員がやっている仕事の多くが実はAIで代替可能となったら、同じ考え方で持続できるとは限りません。
低い給料で高収益の企業も、大量採用していた普通の人材が採用できなくなってきたら、同じやり方で持続させることはできません。
人事は、その時々の環境変化に応じた最適解を冷静に考えられることが大事です。
実力主義 VS 年功序列

今どき、年功序列を全面的に維持している会社は少数派であるものの、年功的要素が残っている会社はたくさんあります。
実力に応じて給与差を大きくつける会社で成長している会社がある一方、
年功的要素を強く残しながら成長している会社もあります。
つまり、どちらが正解ということはありません。
時代的には「年功序列=時代遅れ」みたいな価値観はあるものの、それが全ての会社に当てはまるかというと、そんなことはありません。
ある会社の社長が仰っていました。
「年功序列は実はメリットがたくさんあるんですよ。人事評価にそこまで正確性を求める必要がなく、評価者の評価能力不足もさほど問題にならず、給料をめぐる揉めごとも起きづらい。社員は年を重ねると生活にお金がかかるので、それに応じて給料が上がっていく。先輩後輩の給料逆転がないから先輩が後輩によく教える。飲み会でも上の人が多めに払いやすく、若手は参加しやすい」
なるほど!と思わされる意見です。
もちろん年功序列はデメリットもありますが、会社が発展していく上で何が最適か?を考える上では、
「年功序列=時代遅れ」という先入観は不要です。
人事はもっと広くフラットに色々な選択肢を考えた上で、「自社に最適な方法」を選んでいかねばなりません。
残業ゼロ VS 法定時間ギリギリまで残業

厚生労働者は立場上、できるだけ企業の残業を減らすよう働きかけ、ルールを作ります。
しかし、厚生労働省は各企業の業績責任など1ミリたりとも背負ってくれません。
人材育成に対しても関心を払ってくれません。
よって、「厚生労働省が〇〇と言っているから」という理由だけで人事が動くとしたら、それは非常に恐ろしいことです。
法律は守らねばなりませんが、企業の業績、社員の成長に責任を持つのは企業自身です。
「残業ゼロ」にして、とことん家庭との両立がしやすい環境を作ることで、自社の社員の力を最大限引き出せる。
さらにそれが採用競争力につながるならば、それが正しい意思決定です。
一方、「社員の成長意欲が非常に高い」「若い社員がもっと仕事して成長したいと思っている」ならば、残業ゼロ施策は逆効果です。
優秀な社員が「こんなゆるブラック企業では成長できない」と感じて辞めてしまうでしょう。
成長意欲の高い社員集団である場合、残業可能な範囲でできるだけ自分の仕事を突き詰め、考え抜いて仕事をしてもらう。
そうすれば、後に大きなリターンとなって本人にも会社にも返ってくるはずです。
つまり、「残業を減らすこと」は目的ではなく、「どんな働き方が社員と会社の成長を最大化するかを見極める」ことなのです。
トップダウンの社風 VS ボトムアップの社風
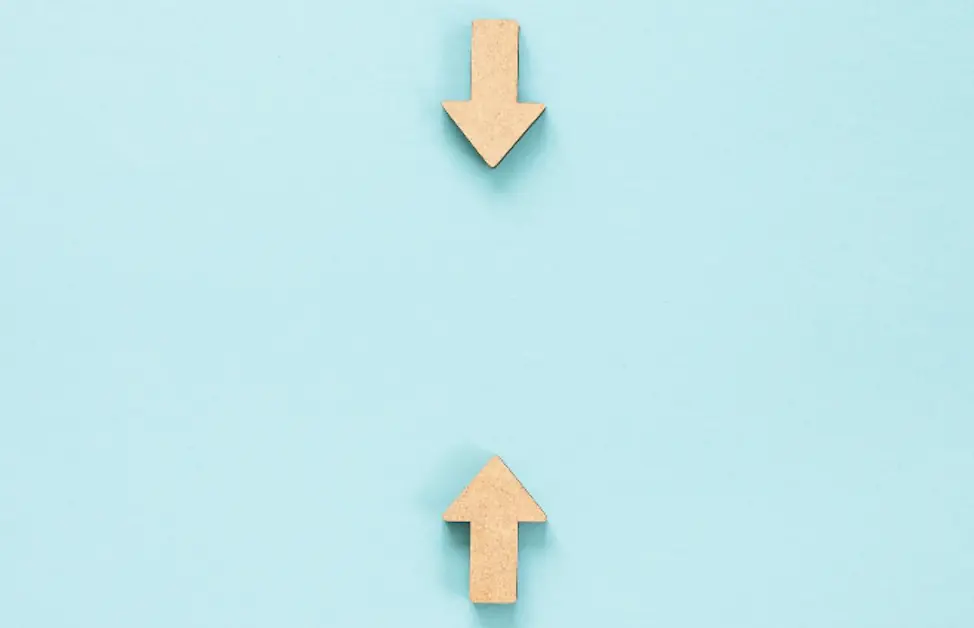
トップダウンかボトムアップかの議論になると、多くの社員が好むのはボトムアップです。
人事の仕事に携わる方としても、ボトムアップ風土の方が人事としてやれる事が多いので、そちらに偏りがちな人もいます。
しかしこれにも正解はありません。
ここでは割愛しますが、トップダウン、ボトムアップ、いずれにもメリットデメリットがあります。
会社の規模、歴史、経営者のスタイル、社員の成熟度、事業の変化スピード、事業戦略戦術などによって、その時とるべきスタイルは変わります。
双方の組み合わせ型もあります。
会社の当面の業績と将来の成長のバランスを見ながら「今ふさわしいのはどのようなスタイルか?」を真剣に考え抜き、トップと徹底議論しながらあり方を決めていくのが人事の重要な役割です。
「私はボトムアップの社風が好き!」 これは個人の思想です。
一社員がそう思うのは自由ですが、人事はそのような思想に左右されることなく、冷静に客観的な視点を備えておかねばなりません。
人事にありがちな誤解
人事に必要とされる二律背反の観点についていくつかの具体例を見てきました。
部長クラスの方に「所属企業を退職する理由」を聞いてみると、
人事部長の場合
![]() 「社長の考えと合わなかった」
「社長の考えと合わなかった」
![]() 「自分の考えと社風が違った」
「自分の考えと社風が違った」
などが他の職種に比べて多いように思います。
人事の仕事はデジタルに答えが出るものではないため、お互いの考えが歩み寄らず、平行線のまま相容れなくなるケースが多いのかもしれません。
ただ客観的に見ていると、
人事部長の中には、ご自身の「組織とはこうあるべき」「人事ポリシーはこうあるべき」という強い考え(思想)があり、それをどこの会社にいっても当てはめようとする方がいます。
患者の状態に関係なく、誰に対しても同じ処方箋を出すお医者さんみたいな感じです。
しかし、実際の企業経営はそう単純ではありません。
先の二律背反の事例のように、人事と経営者で相談する意思決定のうち、多くのことは極と極の間のゾーンにおいて、どこに答えを出すか?という仕事です。
その答えは個人の思想にはなく現場にあるということを忘れてはなりません。
自分の考えや哲学を持つのは大切なことです。
しかしそれはそれとして、いったんゼロベースでフラットに物事を見る視点、会社の今の状態にとって何が最適かを導き出す思考こそが、人事に不可欠な資質です。
まとめ
人事の仕事、特に人事の方針や施策を決める仕事には絶対的な答えがありません。
経理の原価計算手法や帳簿のつけ方は、時代が変わっても会社が変わっても大きな違いはありませんが、人事の施策は時代、事業環境、組織風土などによって最適解が変わります。
答えが曖昧であるがゆえに、人事の世界では個人の思想や理想が強く主張されることがありますが、現実解はそう単純ではありません。
二律背反する考え方のどちらも理解しながら、自社にあった最適解を探るのが人事の仕事です。
広い知識、客観的視点、バイアスを排した冷静な思考の上で、社内外の環境変化に敏感で、関わる人達の心を深く洞察する。
人事とは、まさにそのような総合知と感性が試される、奥深くやりがいのある仕事だと思います。
こちらの記事もおすすめです。












