部下マネジメント
部下マネジメント
マネージャーの育成は人材育成の主要テーマです。
企業規模を問わず、組織の成長にはマネージャーの力量が大きく影響します。
しかし、中小企業ではマネジメント研修に十分な予算を確保しづらく、社内にはロールモデルとなるマネージャーが限られるため、育成がなかなか難しいのが実情です。
とは言え、外部の研修会社にお願いして研修を実施するのが難しくとも、社内でやれることは十分あります。
少なくともマネージャーがどのようなスキルを身につけるべきかを明示し、社長が経験談を伝えたり、先輩が手弁当で教えたり、マネージャー同士が勉強会を行うだけでも組織のマネジメント力は確実に底上げされます。
今週のブログでは、マネージャーが習得すべき、部下マネジメント&チームマネジメントの必須メニューについてお伝えします。
目次
マネジメント力を向上させるメリット

マネージャーは会社の方針をメンバーに伝え、業績責任を背負い、部下の育成とサポートを担う「組織の要」です。
重要な役割であるだけでなく業務が多岐にわたり手間のかかる仕事でもあるので、近年は「マネージャーに昇格したくない」という声も増えています。
”割に合わない仕事”と思われてしまっているのかもしれません。
しかしながら「マネジメント力」は会社の内外を問わず、どんな組織においても通用する非常に強力なポータブルスキルです。
大変な役割ではありますが、その分AIに置き換わりにくい普遍的な能力でもあります。
企業にとっても、マネージャー層の厚みが出れば組織の成長スピードが大きく加速しますので、「マネージャーの育成」には十分に力を入れてほしいと思います。
チームマネジメント・ 部下マネジメント 育成の必須メニュー
以下は、チームマネジメント&部下マネジメントを習得するための11個の必須メニューです。
1 マネージャーの役割理解
2 マネジメントとリーダーシップの理解
3 チームビルディング
4 対人コミュニケーション
5 チームコミュニケーション
6 動機づけ
7 人材育成・フィードバック
8 ファシリテーション
9 業務の割り振り
10 情報設計
11 組織活性化
(必要な場合)リモートワークマネジメント
それぞれで習得すべき内容について見ていきましょう。

マネージャーの役割理解
マネージャーに見られる課題の1つは、マネージャーという仕事に求められる役割を正しく理解できていないため、思いついた仕事や時間の許す範囲でできる仕事だけをやっていることです。
従って、出発点は「マネージャーとはどのような役割か」を理解することです。
チームの業績を出すことはもちろんですが、部下の育成・サポート、組織のハブ機能、中長期に向けた課題の解決など多岐にわたります。
評価、勤怠承認、稟議承認、リスク管理などアドミ業務もあります。
多くのマネージャーは自分自身のプレイヤー業務も抱えているため、限られた時間の中でマネージャーの役割をどのように全うすべきか、時間配分をよくよく考えた上で船出していく必要があります。
マネジメントとリーダーシップの理解
マネジメントとリーダーシップは異なる役割でありつつ、連なるところもあります。
![]() マネジメントは「適切に運営し、成果を出すこと」
マネジメントは「適切に運営し、成果を出すこと」
![]() リーダーシップは「未来の行先を掲げ、そこに導き変革していくこと」
リーダーシップは「未来の行先を掲げ、そこに導き変革していくこと」
その違いを理解した上で、自分がどのように振る舞うかを考えてもらいましょう。
組織の局面やマネージャー自身の置かれている環境によって異なるので、自分がマネジメントの役割とリーダーシップの役割をどう演じていくかを判断する必要があります。
チームビルディング
良いチームと悪いチームの違いを理解する必要があります。
良いチームの条件は古今東西さほど大きな違いはありません。基本セオリーをしっかり抑えましょう。
スポーツの世界でも、企業のケースでも、良いチームの事例はたくさんあるので、そういった教材から具体的に学ぶのも有効です。
マネージャーになったら、ただ漫然とチームを運営するのではなく、
「皆が意欲的に取り組み、活発な意見交換がされ、共に高い目標にチャレンジしていけるチームをどう作るか?」を常に考え試行錯誤していかなければなりません。
良いチームは勝手にできあがるものではなく、マネージャーが意識して作り上げるものであることを理解してもらいましょう。
対人コミュニケーション
各人のコミュニケーションスタイルはそれぞれの過去の経験や考え方によってできあがっていますが、それが仕事のコミュニケーションのあり方として適切であるとは限りません。
仕事では、相手の話にしっかり耳を傾け、相手の言いたいこと(真意)を理解できなければなりません。
自分に良い考えがあっても伝え方が悪ければ相手に伝わりません。いかにわかりやすく平易な言葉で相手に伝えられるかが問われます。
加えて、相手の気持ちを理解し、共感する感情力も求められます。
部下マネジメントでは「コミュニケーションが苦手」と思っていた人は、それを克服しなければなりません。努力で十分克服できるものです。
自分のコミュニケーションスタイルや癖を点検し、仕事上望ましいコミュニケーションに近づけていく意識を持ってもらいましょう。

チーム内コミュニケーション
チームという組織全体のコミュニケーションに目を配ることも、マネージャーの重要な役割です。
「お互いの会話が少ない」
「メンバーそれぞれが特定の人としか話さない」
「最低限のことしか話さない」
「表面的に仲はよいが仕事の厳しい会話は避ける」
これらの状態は、チームコミュニケーションが良い状態にあるとは言えません。
メンバー同士がお互いを理解し、関心をもち、困っていたら助けようと思える組織、協力して何かを成し遂げたいと思える組織をどのように作っていくかがポイントです。
今の自分の組織のチーム内コミュニケーションを振り返り、何が足りないかを考え、その改善策を考えてみましょう。
動機づけ
部下の主体的な取り組み、仕事への意欲を引き出す方法はさまざまです。
職場環境や人間関係、上司のかける言葉、指示の仕方、仕事を通じて感じるやりがいなどによって、部下の意欲は大きく変わります。
「やる気がないのは部下本人の問題」と思い込んでいる上司がいますが、それは大きな誤解です。
「本人の問題以上に環境要因が大きい」ことを理解してもらわなければなりません。
加えて、動機づけにはマズローやハーズバーグなどの定番理論が色々ありますので、理論をしっかり学んでおくこともマネジメントの一助となります。
参考までに、私が研修等でお話している「部下の意欲向上に効果的なこと」はこんなにたくさんあります。
人として尊重する、期待をかける、感謝する、声をかける、たくさんコミュニケーションをとる、仕事を認める、よくやったら賞賛する、権限委譲、フィードバックする、チーム内の関係性の良さ、情報開示、育成(能力をつける)、成長機会、仕事のやりがいを感じてもらう、事業の社会的意義、効率的な業務プロセス、働きやすい環境、納得感のある評価、報酬、上司の人柄や姿勢、先輩や同僚の仕事ぶり、ワクワクする会社の将来像・・・
どれが効果的かは環境次第ですが、色々工夫しがいがありますよね。
部下育成、フィードバック
部下育成!と言われても具体的に何をしたらよいかわからず、「とりあえずOJT」という会社が少なくありません。
しかし、部下を育成する方法や場はいくらでもあります。
仕事の会話においてどのような問いかけをするか?
会議にどのような準備をして参加させるか?
業務日誌にどのような内容を考えて書いてもらうか?
役立つ成功事例や業務ノウハウを自主的に学べる機会をどのようにつくるか?
いつどのように振り返り(内省)を行ってもらうか?
こうした日々の業務のやり方次第で部下の成長は大きく変わってきます。
優秀な先輩がいれば、その先輩に勉強会をしてもらうのも刺激的な機会となりますし、チーム内の成功事例や失敗事例を分析して教材化して学びに用いることも有効です。
既に同じような育成の悩みを克服した他社の事例なども、書籍や動画教材などでよいものがたくさん紹介されています。
今の時代は手間暇かけた研修をやらなくても学べる機会が十分にあるので、部下育成は工夫次第と言えます。
フィードバックの効果を理解する
またフィードバックの絶大な効果も理解しておく必要があります。
年に1回の健康診断をすることで自分の身体の状態を客観的に把握できますよね。
受験生は模擬試験を受けることで、志望校合格に向けた現在地を把握できます。
このように、仕事でも「自分の現在地を知るための仕組み」が必要です。
業績評価は年に1回または半期に1回ありますが、それでは間が空きすぎです。
ちょっとしたことでもよいので、部下には小まめにフィードバックをしましょう。
![]() 「前回よりすごくよくなったね!」
「前回よりすごくよくなったね!」
![]() 「だいぶ先回りして考えてくれたね!」
「だいぶ先回りして考えてくれたね!」
![]() 「今日の商談はお客さんに響いてたよ!」
「今日の商談はお客さんに響いてたよ!」
![]() 「商談の説明が盛りだくさんだったから、もう少しコンパクトに伝えられるよう考えてみて」
「商談の説明が盛りだくさんだったから、もう少しコンパクトに伝えられるよう考えてみて」
![]() 「分析資料を読み手視点で見直すといいよ。特にグラフの見せ方とか」
「分析資料を読み手視点で見直すといいよ。特にグラフの見せ方とか」
![]() 「自分なりによく考えられているから、今度は〇〇先輩に見せて違う視点をもらうといいよ」
「自分なりによく考えられているから、今度は〇〇先輩に見せて違う視点をもらうといいよ」
このように、ちょっとした成長を認知させ、次の進歩への課題を伝えることで、部下の成長スピードを加速させられます。
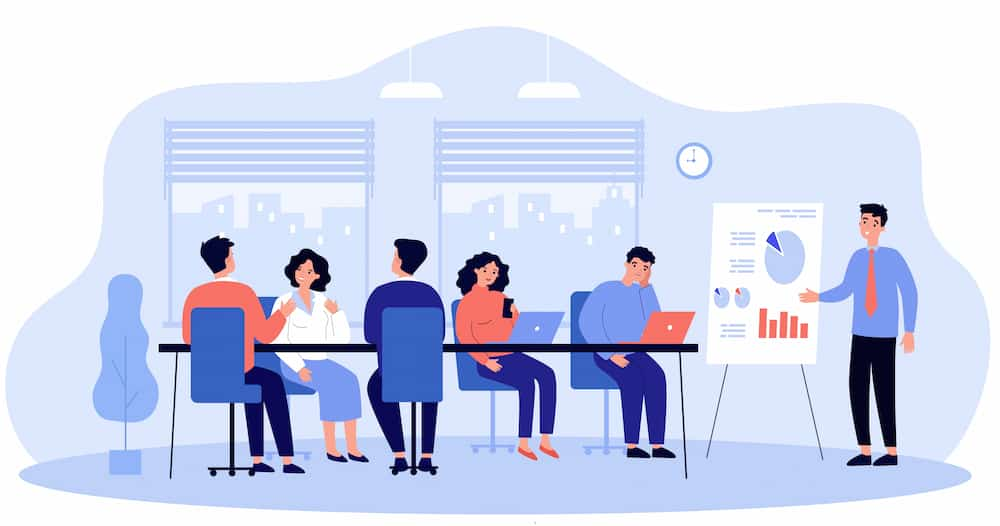
ファシリテーション
ファシリテーション力は組織の力を引き出す上で非常に有効なスキルです。
会議を効率よく進め、多くの意見を引き出し、望ましい結論に導いていくのがファシリテーションです。
ファシリテーションを学んでいないと、目的のよくわからない会議、ダラダラ会議、上司だけがしゃべり続ける会議、何も決まらない会議などが横行しかねません。
ファシリテーション力は練習すれば誰でも上手くなるスキルです。
だからこそ、マネージャー全員が身に着けるべきコアスキルだと考えています。
業務の割り振り
部下に業務をどのように割り振るかは、多くの場合マネージャーに一任されています。
マネージャーはどのような判断基準で割り振りを行っているでしょうか?
割り振りにおいては、片側に「業務の目的、アウトプット、遂行に求められる能力、必要人員、期限」などを考えつつ、もう一方では「社員の能力、経験、現在の業務状況、本人のやりたい事、今後の成長に必要な経験」などを両面から考えて、誰にその仕事を振るかを決めていきます。
特定の人に偏る配分は持続性がありません。
ずっと同じ仕事ばかりさせていると成長がありません。
チームが持続的かつ安定的に発展していくための仕事の割り振りを考えてもらいましょう。
情報設計
耳慣れない言葉だと思いますが、情報をいつ誰にどのような方法で伝えるかを「情報設計」と呼んでいます。
「設計」という言葉を使うのは、マネージャーに「意図をもって情報を扱ってもらいたい」からです。
例えば情報には、その時伝えれば済むフローの情報と、蓄積するストックの情報があります。
ストックの情報とは、データの推移を見て分析するようなものや、貴重なナレッジとして後々参考にするために保管する情報です。
本来ストックすべき情報でありながら、メールで軽く共有されただけ(=フローとして扱われた)なので、数ヶ月後に参考にしようと思っても見当たらない・・・なんてことはないでしょうか?
マネージャーがチームメンバーに発信する情報も、目的が色々あるはずです。
「会社全体の動きの共有」「チームの方向性の共有」「業績の進捗共有」「ルールの伝達」「業務ノウハウやコツ」「参考ニュース」などなど。
それぞれの目的によって、発信の仕方や情報を保管する場所、閲覧の方法、閲覧権限の範囲などが異なってくると思います。
それを的確にコントロールするマネージャーの役割が「情報設計」です。

組織活性化
チームは順調な時もあれば、何かをきっかけにメンバーの士気が下がったり、離職が増えたりするピンチもあります。
上記でお伝えしてきた内容を普段から地道に積み重ねていくことがチームの停滞を防ぐ防御策になりますが、危機を迎えた時には特別な活動も必要になります。
例えば、業務量が膨大で、お互いの会話が減り、仕事の押し付け合いが始まり、相互不信が募ってきたとき、あなたならどのように打開しますか?
組織に関わる改善施策はデジタルには答えが出てきません。
状況次第で解決策も異なりますが、何か策を講じてみる勇気は必要です。
このケースであれば、例えば以下のような方策が考えられます。
![]() 業務の見直し(不要業務の削減)を皆で集まって徹底議論する
業務の見直し(不要業務の削減)を皆で集まって徹底議論する
![]() 業務外交流の場を通じてお互い相手をもっとよく知る機会をつくる
業務外交流の場を通じてお互い相手をもっとよく知る機会をつくる
![]() オフサイトで時間をとり、改めて今自分の悩み、困りごと、助けてほしいことを共有し合う
オフサイトで時間をとり、改めて今自分の悩み、困りごと、助けてほしいことを共有し合う
![]() 今の状況をどうやったら打開できるか、ワークショップ形式で話し合う(できれば気分が一新できるような場所に移動して)
今の状況をどうやったら打開できるか、ワークショップ形式で話し合う(できれば気分が一新できるような場所に移動して)
![]() マネージャーが今の状況に陥ったことを詫びて、その上で「皆に力を貸して欲しい。以前の良い組織に戻すよう協力して欲しい」と伝える
マネージャーが今の状況に陥ったことを詫びて、その上で「皆に力を貸して欲しい。以前の良い組織に戻すよう協力して欲しい」と伝える
![]() お互いがどのような仕事を行っているかを定期的に共有する場をもうける
お互いがどのような仕事を行っているかを定期的に共有する場をもうける
などなど。
方法は色々ありますが、組織の危機に直面した時、放置せず、悲観せず、具体的に取り組める対策があることをマネージャーは理解しておく必要があります。
(必要な場合)リモートワークマネジメント
リモートワークのメンバーをマネジメントする局面も増えています。
リモートワークには働き手にとって大いにメリットがある半面、チーム内コミュニケーションを高めたり、クリエイティブなものを協働して生み出すのは向かない、部下育成しづらいなどのデメリットもあります。
(ここではリモートワークのメリット、デメリットの詳細は割愛します)
マネージャーが意識すべきは、「デメリットもある」と言う事をチームメンバー皆に周知し、皆で協力しながらデメリットを解消する努力をすることです。
今多くの会社がリモートワーク問題で頭を悩ませているのは、社員がリモートワークの恩恵を享受する一方、発生する不都合や歪みは経営陣とマネージャー側に一方的に積み上がっていくという不健全な構図です。
リモートワークにはデメリットもある事が既に証明されている以上、対立構造で解決すると良い結論になりません。
関わる全員で「リモートワークのメリットを持続するために、どうやったらデメリットを解消できるか?」を常に考え、議論し合い、ルールづくりや相互補完を行っていくことが必要です。
いいマネージャーがいるチーム
いいマネージャーがいるチームとそうでないチームの違いはどこにあるでしょうか?
メンバーの表情や会話を見ているとそれはすぐにわかります。
![]() いいチームは目がキラキラし、お互いのコミュニケーション頻度が高いです。
いいチームは目がキラキラし、お互いのコミュニケーション頻度が高いです。
![]() ちょっとした立ち話、相談、声掛けがたくさん発生しています。
ちょっとした立ち話、相談、声掛けがたくさん発生しています。
![]() チームのゴールを皆が理解し、そこに向けて率直に議論します。
チームのゴールを皆が理解し、そこに向けて率直に議論します。
![]() 厳しい意見も言い合いますが、ベースとなる相互理解、相互信頼があるので、雰囲気は悪くなりません。
厳しい意見も言い合いますが、ベースとなる相互理解、相互信頼があるので、雰囲気は悪くなりません。
![]() ゴールに向けて力を合わせる意味を理解し、その高い目標にこだわりを持っています。
ゴールに向けて力を合わせる意味を理解し、その高い目標にこだわりを持っています。
![]() できない時は相談し、必要に応じで仲間の力を借ります。
できない時は相談し、必要に応じで仲間の力を借ります。
![]() 虚勢をはることはしませんが、弱音や言い訳は滅多に出ません。
虚勢をはることはしませんが、弱音や言い訳は滅多に出ません。
マネージャーがこんなチームを作れるようになることが、部下マネジメント力・チームマネジメント力を高める目的です。
まとめ
マネージャーの育成は、中小企業にとって避けて通れない重要なテーマです。
豊富な研修予算や立派な仕組みがなくても、必要なスキルを明確にし、日々の業務の中で学び合い、工夫を重ねていくことでマネジメント力は確実に高まっていきます。
今回紹介したスキルはどれも日常の職場の中で実践しやすいものばかりです。知っているか知らないかだけでも大きく変わります。
参考になる本もたくさんあります。
マネージャーたちがこうしたコアスキルを身につけていけば、組織の力は大きく底上げされるでしょう。
さらなる会社の成長に向けて、ぜひマネージャーの育成に取り組んでいただきたいと思います。
こちらの記事もおすすめです。












