人事施策
人事部はさまざまな役割を内包した部門です。
採用、配置、育成、人事制度(評価/給与/等級など)、人件費管理、給与計算、労務管理、企業風土づくり、働きやすい職場/制度づくり、などの役割があります。
役割が多いがゆえに、起こりやすいのが「合成の誤謬」です。
合成の誤謬とは、「ミクロの視点では正しいとされる行動が、マクロの視点では望ましくない結果をもたらしてしまう」という論理的な矛盾のことです。
採用は採用、育成は育成、労務は労務と、担当者はそれぞれ「自分の領域で最適な仕事」をしようとします。
ところが、それらの施策を組み合わせたときに全社としての一貫性が失われ、「結局、何を目指しているのか」が曖昧になってしまうことがあります。
今週のブログでは人事で発生しがちなこの「合成の誤謬」を掘り下げてまいります。
目次
合成の誤謬の例

クラウドツールを手掛けている社員200人ほどの会社(A社)の事例です。
業績好調で社員もどんどん増加中の会社です。
A社の人事部はよく働くスタッフが揃っており、社外のセミナーや勉強会にも積極的に参加し、最近の人事の潮流も抑えています。
とても仕事熱心で、皆が会社をよくしようと奮闘している組織です。
人事部長は長らく給与計算や労務管理を担当していた人で、人事企画や育成などはあまり経験がなく、担当者の考えを尊重するスタイルです。
ここ1年程度で人事が進めた代表的な施策と結果は次の通りです。
施策と結果
採用![]() 新卒採用を今年からスタート
新卒採用を今年からスタート
→ かなり労力を投入し5人内定
育成![]() 全社員が自主的に学べるよう受け放題のオンライン教育システムを導入
全社員が自主的に学べるよう受け放題のオンライン教育システムを導入
→ 社員が皆忙しくて利用は低調
![]() 外部の研修会社に依頼して管理職向けの2日間のマネジメント研修を実施
外部の研修会社に依頼して管理職向けの2日間のマネジメント研修を実施
→ 研修は行ったが、その後のフォローなどがなく特段の効果が出ていない
働きやすい職場づくり
![]() 元々max週1日のリモートを3日に拡大
元々max週1日のリモートを3日に拡大
→ 3日間利用する社員が増えたが、マネージャーからは部下の管理がしづらくなったとの声
健康経営![]() 残業時間削減運動
残業時間削減運動
→ 月間15時間以内を目標とし、かなり目標に近づいてきた
人事制度![]() 目標管理の導入
目標管理の導入
→ 目標の設定にバラつきがあり、目標に向けたPDCA管理もうまく回っておらず中途半端な状態
人事データ活用
![]() 今後の人事データ活用に向けてタレントマネジメントシステムを導入
今後の人事データ活用に向けてタレントマネジメントシステムを導入
→ 導入したが、一部の機能以外ほとんど使われていない
いずれの施策も「良かれと思って」進めたものですが、全社視点で見るとどうでしょうか?
A社の課題と経営の方向性

人事施策は、会社の現状と課題あってのものなので、少しA社の前提をお伝えします。
A社はもともと、業界でも独自のポジションを持つ商品力、高い収益性、社員同士の仲の良さ、定着率の高さ、社長以下フランクで何でも言える組織風土、などが強みでした。
リファーラル採用で入社した社員も多くいます。
一方で弱点も見えていました。
A社は厳しさに欠けるところがあり、会社が立てた目標に到達しなくても「まあ仕方ないよね」といった雰囲気がありました。
管理職も総じて数字に対するこだわりが弱く、「優しくて部下に好かれる上司」ばかりで「厳しいが成長させてくれる上司」がいない状態でした。
マネジメント手法も体系化されておらず、各人が我流でやっている状態。
PDCAサイクル(目標設定→実行→振り返り→改善)をしっかり回せている上司は稀でした。
そのようなA社が、投資家から資金調達し、いよいよ上場を目指すことになり、一段ギアを上げた成長が求められるようになりました。
そして、次なる成長に向けて克服すべき経営の優先課題は以下の3点でした。
A社の優先課題
![]() これまでの問い合わせ営業スタイルから、市場開拓型の狩人営業へのスタイルの転換。営業の大幅増員
これまでの問い合わせ営業スタイルから、市場開拓型の狩人営業へのスタイルの転換。営業の大幅増員
![]() 「関係性の良さ」という長所は残しながら、ぬるま湯的なマネジメントから結果にこだわる厳しいマネジメントへの転換
「関係性の良さ」という長所は残しながら、ぬるま湯的なマネジメントから結果にこだわる厳しいマネジメントへの転換
![]() 部署目標、個人目標を設定し、その目標に向けて各組織、各社員のPDCAが回っている状態の確立
部署目標、個人目標を設定し、その目標に向けて各組織、各社員のPDCAが回っている状態の確立
この3つを達成するためには、本来なら人事のリソースもここに集中させる必要があります。
しかし、上述の直今1年で進めてきた人事施策は一部ちぐはぐであったり、戦力分散が生じてしまっています。
施策の見直しポイント

先ほどの人事施策は、会社が現在抱える課題と上手く連動しておらず、部分最適になっていました。
ではどのように見直しすればよかったでしょうか?
採用
育成に時間のかかる新卒採用よりも中途採用で即戦力の営業人材確保に注力すべきだったのでは?
育成
全社員の教育は後回しにして、管理職研修に集中すべきだったのでは?
(ありきたりの管理職研修ではなく、厳しさのあるマネジメントに転換するためのトレーニング、改善のフォローアップ、管理職お悩み相談、相互勉強会など、色々な方法を通じて、全社的に管理職の育成を特化)
働きやすい職場づくり
リモート勤務日数が増えるとマネージャーの部下マネジメントが難しくなるので、週3日への拡大はマネジメント育成強化の後でもよかったのでは?
健康経営
多少残業が増えてでも営業スタイルを転換すべきタイミングなので、この1年は残業削減を掲げる必要はなかったのでは?
人事制度
人事として目標管理の導入にとどまらず、適切な目標設定の指導、PDCAサイクル確立の支援にまでリソースを投入してもよかったのでは?
人事データ活用
将来的にデータ活用は必要だが、今はまだ使いこなせないので、その導入にかけるエネルギーを他の優先課題に回しても良かったのでは?
以上のように、全社観点では人事の施策間に矛盾や非効率が生じ、むしろ逆効果になっていた部分もありました。
正にこれぞ「合成の誤謬」です。
個々の担当者はそれぞれ
![]() 「社員の体が資本なので健康経営を推進すべき」
「社員の体が資本なので健康経営を推進すべき」
![]() 「子供がいる社員がより働きやすいようリモートを促進しよう」
「子供がいる社員がより働きやすいようリモートを促進しよう」
というように、良かれと思って推進していました。
ところが、それらが同時に走ったとき、本来経営が優先すべき営業改革や管理職育成への集中が薄れ、成長加速のチャンスを逃しかねない状況になってしまうのです。
人事部門は多くの機能をもっており、それぞれの機能が縦割りで動きがちです。
合成の誤謬が起きやすい部署と言えるでしょう。
全てに優れた会社はない 凸凹をつくる勇気が必要
会社の魅力や優位性は凸と凹の組み合わせです。
サッカーに攻撃型と守備型のチームがあるように、会社も同様に「尖った強み」が必要です。
人事面において、採用力が断トツ、教育の仕組みも断トツ、働きやすさも業界トップ、給料水準も業界トップ、チームワークも断トツ、関係性も最高!
・・・なんて会社は恐らく存在しないでしょう。
ということは、大事なのはメリハリです。
「採用力は弱くて優秀な社員は採れないけど、育成力が強いのが当社の強み」
というように、強いところと弱いところのメリハリで会社の個性が決まります。
凸凹のある会社のほうが魅力的
仮に組織の強さをあらわす要素として5つの項目(採用力、育成力、働きやすさ、チームワーク、報酬水準)を点数化したとしましょう。
Y社 すべてが3.5点(平均より少し上、でも飛び抜けたものはなし)
Z社 チームワーク5点、働きやすさ4点、報酬水準3点、採用力と育成力は2.5点(平均3.4点)
どちらの会社が「人事的に強い」でしょうか?
Y社は全てが3.5点ということは、明らかに劣っているものはなく、いずれも平均よりちょっと上ですが、特にいいものもない。
つまり人事面における会社の個性が見えにくい状態です。
社員から大きな不満は出ないものの、特に満足する点もありません。
一方のZ社は、弱点もあるけれど、職場の人間関係や働きやすさが非常に高いので、それを重視する人にとっては他社にない断トツの魅力を備えています。
Z社は報酬は並、育成のための研修などもなく、人が足りなくてもなかなか採用できない会社ですが、それでも「この会社が好き」と思う人がいるのではないでしょうか。
中小企業は社員数も限られるので、万人に受ける会社を作る必要はありません。
会社の特徴や価値観に合った人が来てくれればよいので、強いところは明確に尖らせ、そうでない部分は致命的にならない程度に調整すればいいでしょう。
「人事戦略」とは、経営の方向性に沿って、凸凹「どこを強くし、どこをあえて強化しないか」をデザインすることです。
全ての要素を一律に高めていこうとするのは戦略なき人事です。
幹と枝葉、今と将来を明確に
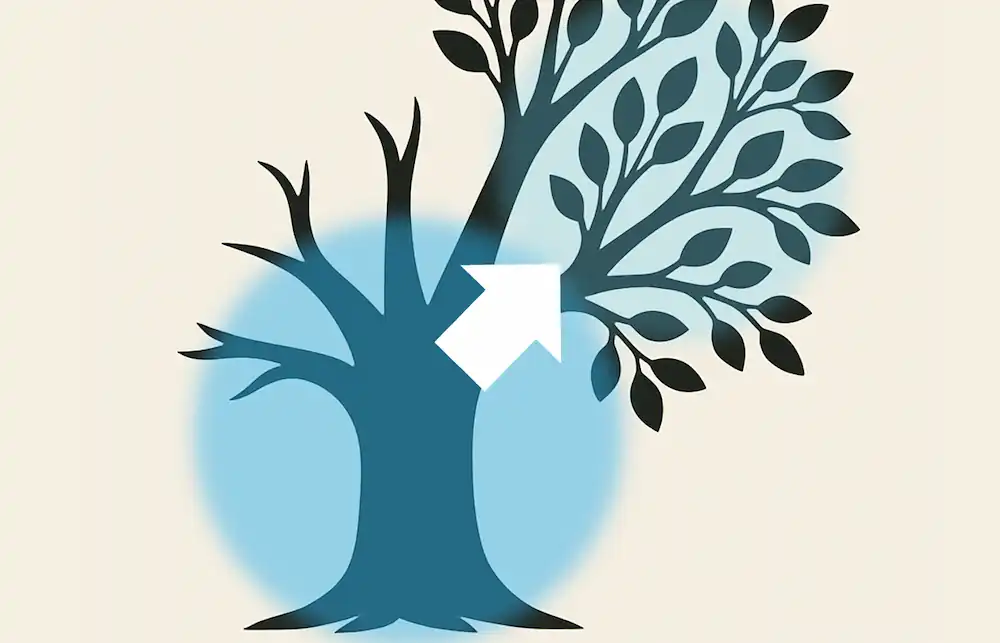
先ほどのA社の人事施策においては、会社の3つの課題を軸に据え、そこから人事施策につなげていくとスムーズに考えられます。
施策の幹は3つの課題を直接解決するものです。
![]() 管理職の育成
管理職の育成
![]() 目標管理制度の運用徹底
目標管理制度の運用徹底
![]() 営業即戦力の中途採用強化
営業即戦力の中途採用強化
この3つがコア施策となります。
ここにエネルギーの8割をかけ、徹底的に進めます。
その上で、段階的により強い会社を築くための次のステップとして、
![]() 新卒採用スタート
新卒採用スタート
![]() 管理職育成に続いて、次なる育成ターゲットの強化
管理職育成に続いて、次なる育成ターゲットの強化
を段階的に進めていくといいでしょう。
さらに成長に向けて組織基盤を整える枝葉の施策として、
![]() 健康経営の一環としての残業削減
健康経営の一環としての残業削減
![]() 子育てパパママの働き易さを促進するリモート勤務日拡大
子育てパパママの働き易さを促進するリモート勤務日拡大
![]() 人事データの活用
人事データの活用
などを進めていくのが順当な流れではないでしょうか。
会社の置かれている環境によって、何が幹で何が枝葉かは異なります。
「今やるべきこと」と「将来やるべきこと」を切り分け、優先順位を明確にすることが大切です。
まとめ 人事の仕事の目的

当たり前の事ですが、人事の仕事の目的は経営ビジョンや経営戦略の実現にあります。
採用、育成、制度、労務、働きやすさといった各領域をそれぞれを一律に改善することが仕事ではありません。
経営が今、どのゴールを目指しているかによって、何に力を配分すべきかが決まります。
- 採用力を徹底的に高める必要があれば、それがメインタスクとなる
- 育成力で競合に圧倒的な差をつけることが必要なら、育成施策にリソースを投下する
- 育成を強化する場合であっても、現場担当者の実務スキルを高めるのか、経営幹部のリーダーシップを高めるのか、会社として今何が最も必要とされているか次第で打ち手を変える
このメリハリ思考=凸凹政策をどのように進めていくかが、人事の腕の見せどころです。
人事の個々の担当者は、どうしても自分の受け持つ範囲の仕事を良くしようと考え、結果として個別最適の動きになりがちです。
だからこそ、経営陣や人事部長は全体最適の視点で手綱を取り、バランスを整えることが極めて重要なのです。
こちらの記事もおすすめです。












