現場のリアル
「上、三年にして下を知り、下、三日にして上を知る」という格言があります。
(流通評論家の吉田貞雄氏の著書のタイトルより引用)
この格言の意味は
「上司が部下を正しく判断するには3年かかるが、部下は上司の長所も短所も3日あれば分かる」
というものです。
上司が部下を評価するのはとても難しく、誤りやすいもの。
だからこそ、人を評価する立場にある人は、常にこの戒めを心に刻んでおく必要があります。
今週のブログでは、上司による部下の評価が誤りやすい理由と、それを防ぐための心がけについてお伝えします。
目次
身近で見聞きする登用の失敗

会社勤めの方であれば、このような場面を必ず一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。
「なぜ、あの人が部長になるんだろう?」
部長候補のうち、周囲が一番部長に向かないと思っている人、部下から信頼のない人が部長に選ばれてしまうのです。
選んだのは社長なので従うしかありませんが、現場は不安と戸惑いに包まれます。
選ばれた新部長のAさんは、社長に絶対服従で、社長から言われたことはすぐにやります。
(正確には、すぐにやるポーズをとり、部下に丸投げします。)
部下への指示は![]() 「社長が〇〇と言っているからやっておいて」と伝えるだけ。
「社長が〇〇と言っているからやっておいて」と伝えるだけ。
自分から動いたりアイディアを出そうとはしません。
指示通りに部下がやっていないと怒鳴りつけますが、成果を出すための協力はしてくれません。

社長に対してはいつもハキハキ、ニコニコですが、部下に対しては不愛想で上から目線。
社長からのメールには即反応しますが、部下が相談事を持ちかけても、ノラリクラリでまともに対応してくれません。
少し誇張しましたが、実際にこのAさんタイプの人が出世する光景を見ることがあります。
Aさんが新部長に就く限り、当然ながら現場の士気はあがらず、部内のコミュニケーションは停滞し、結果としてチームの成果も上がらなくなります。
これは本来社長も望んでいない状態です。
なのになぜ、社長はAさんのことを評価し、部長に抜擢してしまったのでしょうか?
評価が「上から3年」かかる理由

先ほどのケースの場合、社長は新部長に抜擢したAさんの本当の姿を見抜けていなかったことになります。
社長から見たAさんと部下から見たAさん
社長にとってAさんは、このように見えていたことでしょう。
- 自分の指示に対してすぐに行動する
- 指示にしっかり従う
- 仕事をしていてストレスがない
- 素直で可愛らしい
上記の要素はいずれも大事なことです。
仮に、社長の指示に従わない人、行動の遅い人、付き合いづらい人だとしたら、そういう人を部長に登用すべきではありません。
しかしAさんの場合、上司と部下で態度を巧妙に使い分ける「二面性」の持ち主です。
社長からは片方の姿しか見ることができませんが、部下からは両面が見えています。
![]() 社長から電話がかかってくるとまるで別人のように応対するAさん
社長から電話がかかってくるとまるで別人のように応対するAさん
![]() 社長とのミーティングでは部下には見せたことがないような笑顔で相対するAさん
社長とのミーティングでは部下には見せたことがないような笑顔で相対するAさん
そんな姿を、部下たちは日々目にしているのです。
これこそが「上から3年、下から3日」が生じる大きな理由の1つです。
接する時間の長さの差
また、Aさんは(通常の管理職がそうであるように)上司である社長と接する時間よりも、部下や同僚と接する時間の方が長いです。
部下と上司は困難な局面を共にしたり、難しい決断を迫られたり、時には互いの意見が衝突することもあります。
そのような時にAさんがどのように振る舞うかを、部下はその長い時間の中で実によく見ています。
一方で、Aさんが社長と接するのは、定期的な報告会議、たまに社長に呼ばれた時くらいです。
よって、社長がAさんの実像を理解するまでには長い期間をかけざるを得ない構造に置かれています。
上から部下を適切に評価するためには?
では、管理職の部下をできるだけ正しく評価するためにはどうしたらよいでしょうか?
まず肝に銘じておくべきは、「上から3年、下から3日」という格言を忘れないことです。
部下に対する自分の評価は1つの見方でしかなく、それが実態とは乖離がある可能性があると自覚しておかねばなりません。
上司であるあなたが部下のBさんを適切に評価するためには、どのような事を心がけるべきか見ていきましょう。
管理職の部下を適切に評価するために見るべき4つのポイント

チームの成果を見る
![]() Bさんの自分に対する態度よりも、Bさんのチームの仕事の成果を見ましょう。
Bさんの自分に対する態度よりも、Bさんのチームの仕事の成果を見ましょう。
- Bさんが自分の指示にすぐに従うかどうかは本質ではありません。指示に従った上で、実際にBさんのチームがその指示を実行して問題を解決し、仕事の成果につなげているかが大事です。
- 自分の指示を素直に聞いたところで、その後Bさんの部署としてチームで取り組み、チームで成果を出せなければ、Bさんは当該部署の管理職としては失格です。
部下の仕事ぶりを見る
![]() Bさんの部下がいい仕事をしているか、成長しているか、定着しているかを見ましょう。
Bさんの部下がいい仕事をしているか、成長しているか、定着しているかを見ましょう。
- Bさんが適切なマネジメントをしていれば、Bさんの部下は積極的に仕事に取り組み、いい仕事をしているはずです。
- Bさんの指導力があれば、部下達は着実に成長し、やりがいを感じ、定着率も高まっているはずです。
チームの士気を見る
![]() Bさんの部署の活力、士気、メンバーの表情などを見ましょう。
Bさんの部署の活力、士気、メンバーの表情などを見ましょう。
- Bさんの指導が適切で、部下からの信頼があれば、Bさんのチームは活力あるよいチームとして機能しているはずです。
- あなたに見えるBさんが優秀な人材であったとしても、チームが停滞しているならば、Bさんの優秀さには疑問符がつきます。
客観的な意見を聞く
![]() Bさんの部下、Bさんの同僚などに客観的な意見を聞きましょう。
Bさんの部下、Bさんの同僚などに客観的な意見を聞きましょう。
- Bさんの部下や同僚に、Bさんの仕事ぶりについて聞いてみましょう。正直に答えてくれるとは限りませんが、ニュアンス含めて伝わってくるはずです。
- Bさんの直部下よりは、隣の島に座っている別部署の同僚の方が、客観的に見ており、利害関係もなく率直に答えてくれるかもしれません。
- 部下や同僚の意見も聞いた上で、自分の評価と照らし合わせれば、バランスのよい評価が得られるでしょう。
(補足)人を見極める別視点

最後に、人を評価する際に参考になる視点があるのでご紹介します。
誰と一緒にいるか
ランチ時やプライベートなどで誰と一緒にいるかは、その人の傾向を物語っています。
いわゆる「類は友を呼ぶ」というように、似た者同士で集まる傾向があるためです。
人は自分と似た人間と一緒にいる方が楽なので、誰と一緒にいるかにその人の内面があらわれます。
上司の前では意欲的、建設的な事を言っている人が、ランチ時はいつもあまりやる気のない集団と一緒にご飯を食べているとしたら、その人は「やる気に欠ける」可能性が高いです。
社外の取引先や派遣社員への対応
社内内部の人には丁寧に対応するのに、取引先にやたら威張る人、派遣社員に偉そうに接する人がいます。
こういう人は相手の立場や権力に応じて態度を変える人なので、リーダーとして要注意です。
社員以外の関係者に評判を聞いてみるのもいいでしょう。
誰をどのように評価するか
その人の部下が5人いたとして、5人の中の誰をどのように評価するかにもその人の内面があらわれます。
えこひいきが極端であったり、自分に従順か否かのみで判断したり、性別や年齢によるバイアスのかかる人もいます。
優秀な管理職であるならば、5人の個々の特徴や強みを抑えた客観的な評価ができるでしょう。
帰社後の夜の過ごし方
会社の外の活動は個人の自由ですが、そこにも人柄が出ます。
同僚と飲みに行く人、翌日の仕事に支障が出るくらい遊び歩く人、勉強する人、社外人脈形成に熱心な人、家庭の時間を大事にする人。
そこにその人の価値観や考え方の一端が見えてきます。
一概に何がよくて何が悪いとは言えませんが、その人なりの考え方があって大切な時間を有効に使えているかは、日常の仕事にもあらわれる注目点です。
まとめ
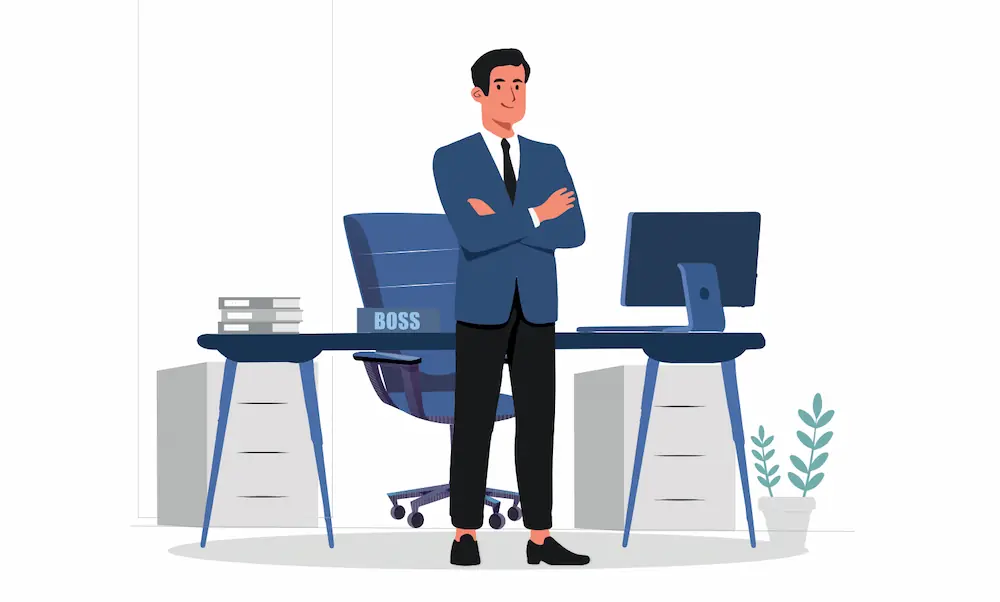
会社において評価を行うのは上司であるにもかかわらず、実は上司には部下の真の姿が見えていないという矛盾が存在します。
とくに、上の人が中間管理職を評価するのは難易度が高いです。
評価を行う人は、「上、三年にして下を知り、下、三日にして上を知る」という格言を常に意識し、自分の見えているものがすべてではないことを忘れてはいけません。
目の前の言動だけでなく、部下が率いるチームの成果や雰囲気、周囲からの声にも耳を傾け、多角的な視点で評価することが求められます。
また、日頃から部下や同僚とのコミュニケーションを大切にし、現場のリアルな姿に目を向けることも、正しい評価につながります。人を見る目は、一朝一夕では養われません。
自分の評価眼を常に疑い、磨き続ける姿勢が、良いリーダーを育て、組織の力を引き出すことにつながります。
こちらの記事もおすすめです。












