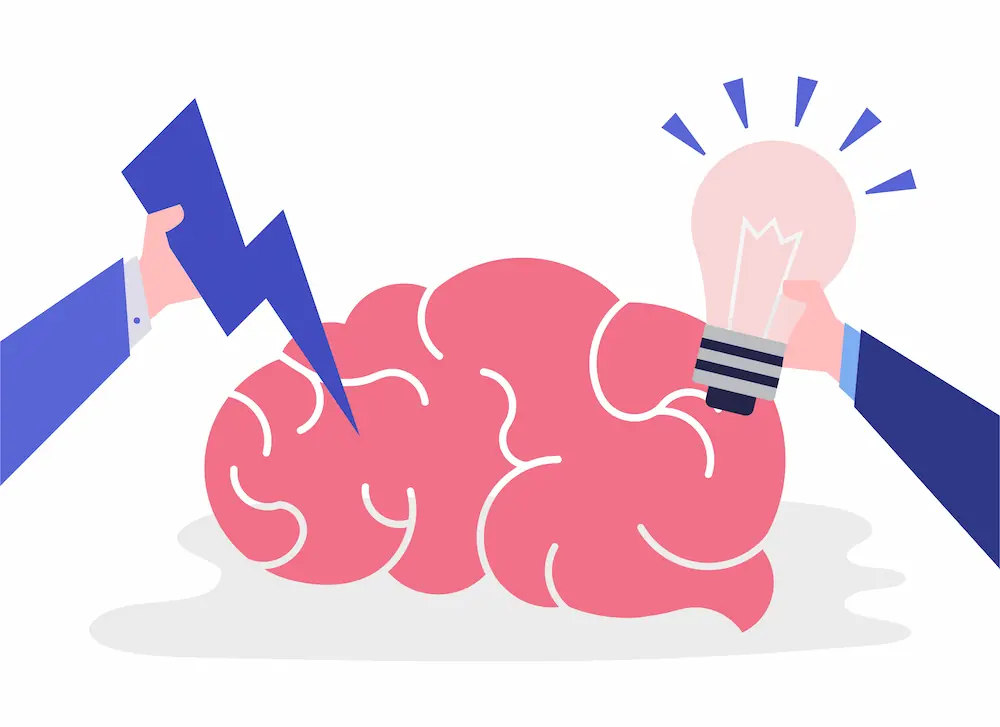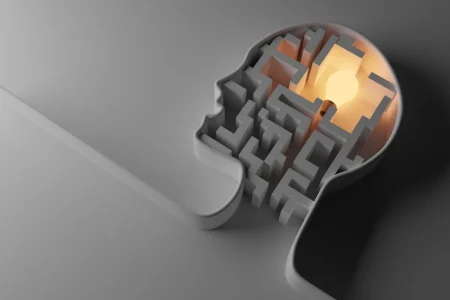考えることが苦手
何か問題が起きたとき、部下に「対策を考えてみて」と宿題を出したのに、思うような答えが返ってこないことがあります。
部下が適切な答えに辿り着けない理由は、本人の能力の問題もありますが、それだけではありません。
実は「考える」ためには「思考法」や「思考プロセス」の基本を理解しておく必要があります。
それを知らないが故に深く考えられていないケースが少なくありません。
このような場合、上司は「考えてみて」と投げかけるだけでなく、もう一歩踏み込んで考え方そのものまでアドバイスをすることで、部下の答えの質を向上させることができます。
今週のブログでは、誰でも一定レベルまで思考できるようになるための、ごく基本的でありながらとても重要な思考法についてお伝えします。
目次
「考える」スキルは仕事に不可欠

「考える」という行為は、具体的に何をすることでしょうか?
勉強においては、「数学の問題を解く」「英作文を書く」「国語で作者の気持ちを考える」などはまさに典型的な「考える」行為と言えます。
一方で、「漢字テストに回答する」「日本史の年号を思い出す」などは、記憶を瞬間的に取り出しているだけで、厳密には「考える」行為とは言いづらいです。
翻って、仕事において「考える」とは何をすることでしょうか?

例えば、営業成績の上がらないAさんに対して、「来週までに対策を考えておいて」と指示したとします。
翌週Aさんが報告してきました。
![]() Aさん「考えました!もっとお客様との商談を増やします」
Aさん「考えました!もっとお客様との商談を増やします」
![]() 上司 「・・・」
上司 「・・・」
上司からすると「本当に考えたのかな?その答えじゃないんだよな・・・」という状態です。
しかし、Aさんは決して「考えなかった」わけではありません。Aさんなりに真剣に考えたはずです。
ただし、その考えるためのプロセスが適切ではなかったため、上司からみると考えていないように見えてしまうのです。
実は多くのビジネスパーソンが「考える」という行為をあまり体系的に理解していません。
それは、上司から教わることも少なく、このようなテーマの研修などもほとんど行われないため、この大事なスキルを身につける機会がないからです。
問題解決の思考プロセス
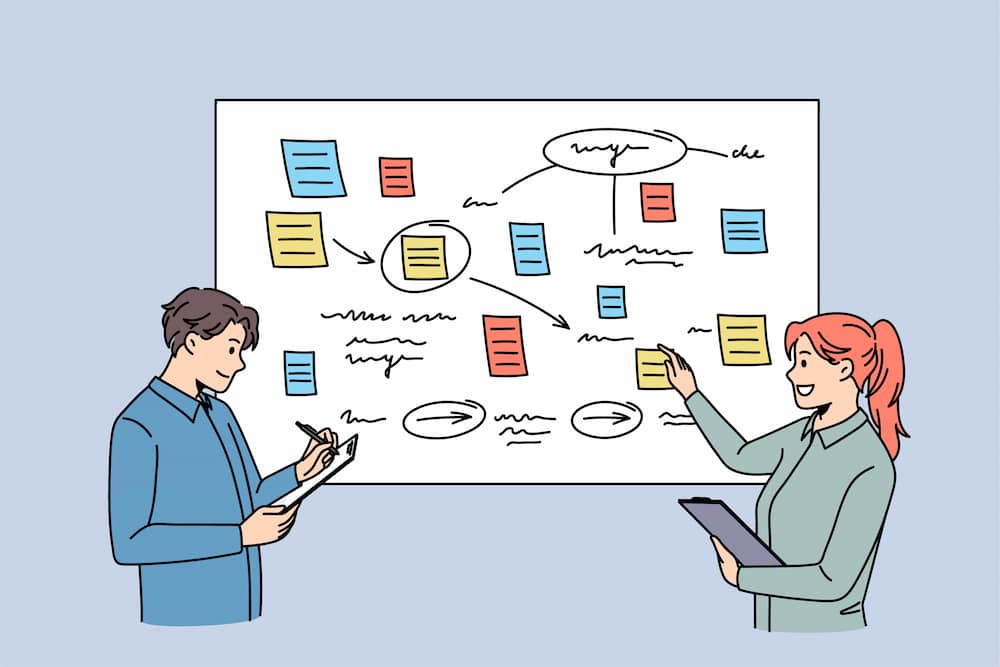
さきほどお伝えした営業のAさんは、上司から宿題をもらった後、週末に悶々と頭を悩ました上で、「自分は商談が少ないから営業成績が上がらない」という結論に達しました。
しかし上司の分析では、Aさんの問題は商談の「数」ではなく「質」でした。
さらに、予算の潤沢な大手企業への営業アプローチが足りず1社あたりの取引単価が低いところにも課題がありました。
Aさんにはこの適切な結論を導くための思考プロセスが欠けていました。
本来Aさんが対策を考える場合に検証すべきこと
![]() 自分の成績を同僚と比較してみる
自分の成績を同僚と比較してみる
(売上、取引社数、取引件数、取引単価、顧客別売上シェア、新規取引件数、新規商談社数など)
![]() 特に成績のいい営業担当者と自分の違いを調べる
特に成績のいい営業担当者と自分の違いを調べる
![]() 特に成績のいい営業担当者の1週間の行動を分析し、自分と比較してみる
特に成績のいい営業担当者の1週間の行動を分析し、自分と比較してみる
![]() 自分の商談のやり方について上司からフィードバックをもらう
自分の商談のやり方について上司からフィードバックをもらう
(本来望ましい商談に比べてどこが足りないかを知る)
このように現状を多角的に分析した上で、自分の業績が悪い原因がどこにあるか、どのような対策が必要かを明らかにするのが、問題解決の思考法です。
問題解決の思考プロセス 3ステップ
整理すると、問題解決の思考プロセスは以下の3ステップにまとめられます。
① 現状分析(自分の営業成績は今どのような状態にあり、その主たる問題点は何か?)
② 原因分析(①の問題が生じている原因は何か?)
③ 対策検討(②の原因を改善するための対策は何か?)
Aさんは①と②を十分に行わずに、いきなり③の対策を考えてしまったため、適切な答えに辿り着けませんでした。
上司が部下に「考えてみて」と指示を出す際には、①~③の思考プロセスについて教えてあげ、その順に沿ってどのように考えるかを事前に擦り合わせておくと良いでしょう。
そうすれば部下の答えの質は飛躍的に高まります。
対策より「真の原因把握」が重要

ちなみに、Aさんのように①と②を省いてしまう問題はビジネスシーンにおいて非常に多く見られます。
例えば、営業部全体の成績が低迷していることに関する対策検討会議で
![]() 「じゃあ、インセンティブの比率を上げよう」
「じゃあ、インセンティブの比率を上げよう」
![]() 「毎朝の朝礼で営業行動の確認をしっかりやろう」
「毎朝の朝礼で営業行動の確認をしっかりやろう」
など、場当たり的な対策ばかりが議論されることがあります。
しかし、営業成績低迷の本質的な原因を正しく把握しない限り、思いつきで出てきた対策は的を得ないものになります。
主たる原因が「商品力の弱体化」であれば商品の改善を、「営業戦略/戦術が時代の変化に対応できていない」なら、その見直しが必要です。
重要なのは、「対策」を考え始める前に、「原因」を的確に把握することです。
真の原因を押さえれば、対策は自然と見えてくるものです。
よって、問題解決の思考においては ①現状分析 → ②原因分析 → ③対策検討 のステップを外さないようにしましょう。
企画業務の思考アプローチ

続いて、企画業務における思考アプローチを見ていきましょう。
企画業務においては、問題解決の思考プロセスに加えて、物事を多様な角度から考え検証するための思考が必要となります。
例えば、あなたを含む同僚3人が上司から「今年の忘年会の企画を考えてください」と言われたら、どのように進めるでしょうか?
考える経験が少ないメンバーは、企画の初回打合せでいきなり次のようなアイディア出しを行うかもしれません。
![]() 1年の区切りだから、盛り上がるように出し物をたくさん企画しよう
1年の区切りだから、盛り上がるように出し物をたくさん企画しよう
![]() 若手が参加したくなるようなイベントを盛り込もう
若手が参加したくなるようなイベントを盛り込もう
![]() 人数が多いから、ホテルの宴会場のようなところで開催しよう
人数が多いから、ホテルの宴会場のようなところで開催しよう
![]() 忘年会だから景気づけにビンゴの商品を多めに用意しよう
忘年会だから景気づけにビンゴの商品を多めに用意しよう
![]() お酒が入ると話を聞かないから、部長の年度総括や表彰イベントは忘年会の前にやろう
お酒が入ると話を聞かないから、部長の年度総括や表彰イベントは忘年会の前にやろう
などなど。
このようにブレスト的にアイディアをたくさん出すのはいいことですが、そこからすぐに結論を出そうと思っても、なかなか良い結論には至りません。
企画精度を高めるための具体的なアプローチ
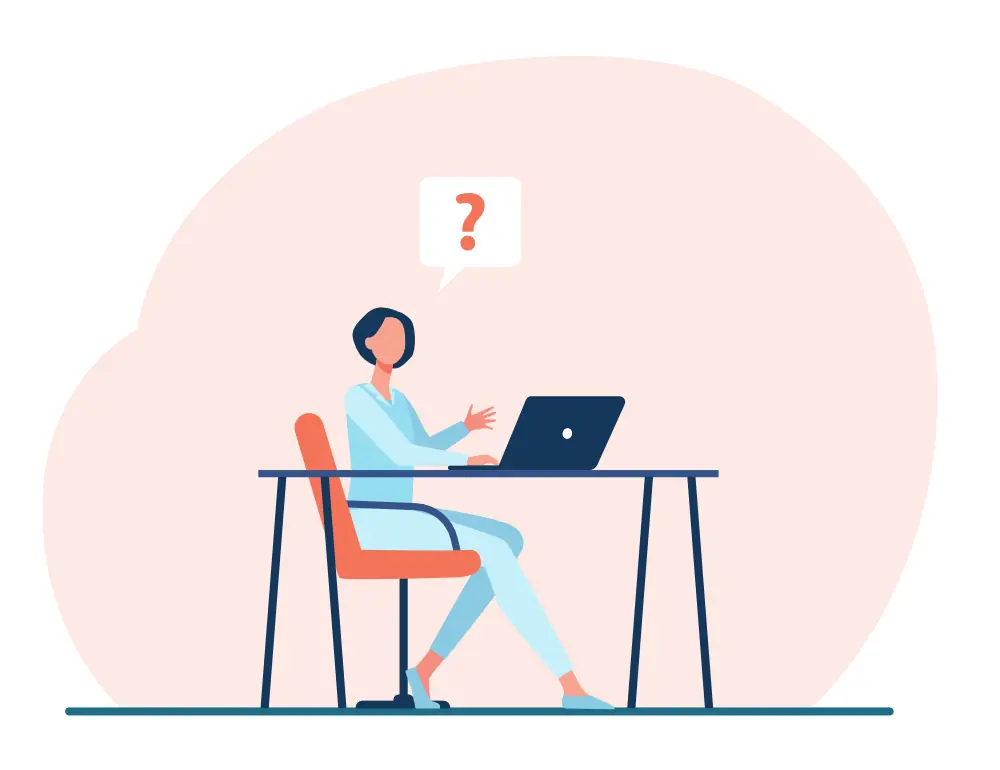
企画の精度を高めるためには、以下のような観点から考えを絞り込んでいくアプローチが必要になります。
具体的アプローチ
![]() 過去の忘年会の良かった点、悪かった点を振り返る(以前の幹事の声を聞く、社員への事後ヒアリング等)
過去の忘年会の良かった点、悪かった点を振り返る(以前の幹事の声を聞く、社員への事後ヒアリング等)
![]() どのような忘年会にしたいか、部長から目的や狙いを確認する
どのような忘年会にしたいか、部長から目的や狙いを確認する
![]() 過去の慣習や制約条件を抜きに、理想の忘年会とはどういうものかを考えてみる
過去の慣習や制約条件を抜きに、理想の忘年会とはどういうものかを考えてみる
![]() 社内で良いアイディアを持っていそうな先輩に意見を求める
社内で良いアイディアを持っていそうな先輩に意見を求める
![]() 知人や取引先などに他社の忘年会でどのような企画をやっているか聞いてみる
知人や取引先などに他社の忘年会でどのような企画をやっているか聞いてみる
![]() ある程度企画が固まってきた段階で、5W1Hなどの観点から議論に漏れがないか検証する
ある程度企画が固まってきた段階で、5W1Hなどの観点から議論に漏れがないか検証する
このようにさまざまな角度から情報を集めることによって、
忘年会に何が求められているか
どのような忘年会だと満足度が高いか
去年の失敗を繰り返さないためにはどうすればよいか
・・・などのヒントが見えてきます。
注目すべきは、上記において行っているアプローチのほとんどが「情報収集」である点です。
「自分の頭の中から何かを捻りだすこと」に費やした時間はほぼありません。
情報収集(インプット)を行うことで脳が刺激される
↓
アイディア(アウトプット)が自ずと浮かぶ
↓
それらを整理整頓しながら結論を考え出していく
という流れです。
仮にインプットが少なければ、ウンウン唸って考えても、よほど経験値の豊富な人でない限り良いアイディアは出てきません。
一方で経験値の少ない人であっても、多彩な角度からインプットを入れれば、一気にショートカットして良い考えに辿り着くことができます。
これこそが良い思考アプローチの醍醐味です。
良い企画というのは、たくさんのインプット、インプットから刺激を受けたアウトプット、それを煮て焼いて練って、他者と議論した上で出てくるものです。
企画の仕事を行う人は、この鉄則を理解しておく必要があります。
企画業務の思考アプローチの整理

上記の忘年会企画で活用した思考アプローチでは、複数の手法が活用されています。
①過去/現在/未来の視点
過去の振り返りを通じて、今後のあるべき姿のヒントを得る
![]() 過去の忘年会の良かった点、悪かった点を振り返る
過去の忘年会の良かった点、悪かった点を振り返る
②目的思考
仕事のそもそもの目的に立ち返って考える
![]() どのような忘年会にしたいか、部長から目的や狙いを確認する
どのような忘年会にしたいか、部長から目的や狙いを確認する
③ベンチマーク
他社や世の中の事例に学ぶ
![]() 知人や取引先などに他社の忘年会でどのような企画をやっているか聞いてみる
知人や取引先などに他社の忘年会でどのような企画をやっているか聞いてみる
④視点ずらし
自分とは異なる人の視点から物事を見てみる
![]() 社内で良いアイディアを持っていそうな先輩に意見を求める
社内で良いアイディアを持っていそうな先輩に意見を求める
⑤理想デザイン
現実や制約に捉われことなく理想的な姿を考えてみる
![]() 過去の慣習や制約条件抜きに、理想の忘年会とはどういうものかを考えてみる
過去の慣習や制約条件抜きに、理想の忘年会とはどういうものかを考えてみる
⑥5W1H検証
企画の論点がある程度出揃った段階で、漏れている論点がないかどうか5W1Hなどのフレームを使って検証する
![]() ある程度企画が固まってきた段階で、5W1Hなどの観点から議論に漏れがないか検証する
ある程度企画が固まってきた段階で、5W1Hなどの観点から議論に漏れがないか検証する
このような思考アプローチは、「考える」仕事のさまざまな局面で使えます。
部下がこのような思考アプローチを知らずに企画を進めようとしているならば、是非その使い方を教えてあげましょう。
何の青写真もなく考え始めるのではなく、よい答えを出すための考える手法をイメージしてから作業に取り掛かかるよう指導します。
まとめ

仕事における「考える」力は、技術を身に着ければ誰でもある程度のレベルには到達可能です。
今回ご紹介した思考プロセスや思考アプローチを当たり前のように使っている人は、周囲から「賢い」「仕事ができる」と見られますが、その大半は訓練の賜物です。
「頭がいいから」できるのではなく、考える方法を学び、考える手法を普段から上手く活用しているからできるのです。
部下の考える力が足りないと感じたら、まずは部下に考える方法を教えてあげましょう。
最後に問題です
「社員が期日までに提出物を出してくれない」という問題を解決するために、あなたの会社ならどのような対策をとりますか?
「期日前の催促の回数を増やす」「部下が期日まで出すよう上司にしっかり伝える」などの思いつき対策に飛びついてはいけません。
まずは、提出が遅れる根本原因を把握すること。
そして、自分の頭で考えるだけでなく周囲からのインプットや外部事例の収集もしながら、ぜひベストな対策を導き出してください。
こちらの記事もおすすめです。