経営幹部登用
経営幹部になるために必要な能力や資質とは何でしょうか?
逆に社長の立場から見ると、どのような条件を満たす人を経営幹部に登用すべきでしょうか?
※ここで言う経営幹部とは、「事業部長、執行役員、取締役」レベルの役割を担いながらも、社長ではない方々を想定しています。
中小企業では、経営幹部を登用する場面はさまざまです。
事業拡大に伴う経営幹部増強であったり、経営陣の世代交代、あるいは「社長1人が牽引する体制」から「経営チームによる運営」への移行など、背景は多岐に渡ります。
ところが、いざ経営幹部に登用しようと思っても「誰を登用すべきか」で悩むことが少なくありません。
特に複数の候補者が横並びの実力である場合、何を基準に、どのような観点で選べばよいかがわからず、決断に迷いが生じます。
将来的に経営幹部を担いたいと思う社員にとっても「明示された基準がないこと」は大きな障害となります。
どのような力をつければ幹部になれるか、目標が見えないからです。
今週のブログでは、経営幹部になるために必要な資質について考えていきましょう。
目次
マネージャー → 経営幹部の「断絶」

私は、経営幹部登用について相談を受けたり、登用までの教育や登用プロセス設計に携わっています。
多くの場合、部長職などでマネジメントを担っている人材の中から経営幹部に登用したり、数年後に経営幹部になれるよう能力開発することがテーマになります。
その時に強く感じるのは「マネージャーとして成果を上げた人が、そのまま経営幹部として通用するわけではない」ということです。
両者の間には明確な”断絶”があり、それを超えない限り経営幹部の仕事は務まりません。
マネージャーの仕事は、マネジメントスキルを積み上げれば、ある程度こなせるものです。
(決してマネージャーの仕事が簡単であるという意味ではありませんので誤解なきよう)
マネージャーは、その役割上「部署の業務運営状況をしっかり管理し、発生する問題を適切に解決し、良いチームを作り、部下としっかりコミュニケーションをとり、人材を育成すること」で十分評価されます。
もちろん、経営幹部の仕事においてもこれらの能力は不可欠ですが、それ以上にもっと強烈に求められるのは、人間性、マインド、リーダーシップなどに関わる内面的な要素です。
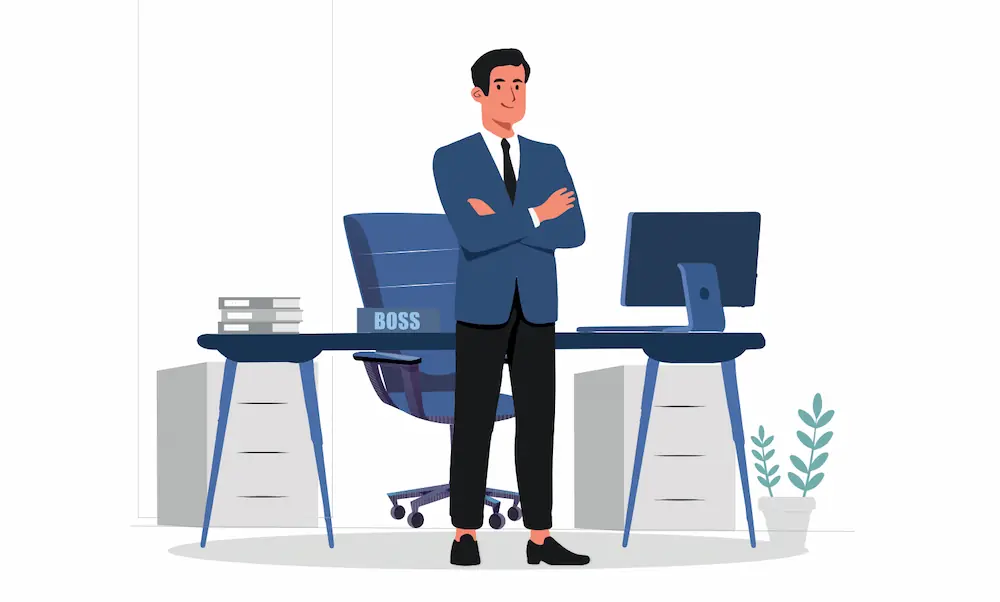
![]() マネージャーに必要なスキルの特徴(例として一部抜粋)
マネージャーに必要なスキルの特徴(例として一部抜粋)
マネージャーに必要なスキルは、たとえば「論理的思考力」「コミュニケーション力」「コーチング力」「業務管理能力」「計画策定力」「評価スキル」「面接スキル」といった、「〇〇力」で表現できるスキルです。
これらは方法論がある程度体系化されているので、学びと実践を繰り返す中で能力値をどんどん高めていくことができます。
また、自分がどの程度のレベルにいるかも一定程度可視化できるので、現在地を把握しやすいものでもあります。
マネージャーに必要な能力の多くは、この「〇〇力」の積み重ねで対応できるものです。
![]() 一方、経営幹部に必要なのは?
一方、経営幹部に必要なのは?
ところが、経営幹部に強く求められる「人間性」「マインド」「リーダーシップ」などは、学習によって積み上げていくスキルとは異なり、日々の仕事の場、鍛錬の場を通じて内部に形成されていく心の在り様です。
そのため、自分がどの程度のレベルにいるかが分かりづらく、他人との比較も難しいので、客観的に現在地を把握できません。
このように、マネージャーと経営幹部の間には「求められる要素の断絶」があります。
経営幹部登用の難しさはここにあります。
多くの場合、マネージャーとして成果を上げた人が経営幹部の有力候補に挙がる一方、実際に経営幹部に+α求められる資質は「マネージャー時代の成果の裏付けとなった能力とは異なるもの」だからです。

よって、経営幹部に求められる資質を明らかにすることには大きなメリットがあります。
マネージャーが早い段階からその事を知っていれば、自分の課題に気づき、能力開発に活かすこともできます。
経営幹部登用を選考する側も、幹部人材を選定するための要素が明らかになっていれば、一部の目立つ成果だけに引っ張られたりすることなく、的確な人選が可能になります。
経営幹部に必要な資質/登用条件
経営者に求められる条件や資質については多くの書籍や論考で語られていますが「社長ではない経営幹部」に必要な資質となると、意外とまとまった情報がありません。
そこで、私がこれまで関わってきた100人程度の経営幹部の方々を1人1人思い浮かべながら作成したものを共有します。
![]() 上手くいった人/卓越した成果を上げた人の特徴は何か
上手くいった人/卓越した成果を上げた人の特徴は何か
![]() 期待に応えられなかった人は何が欠けていたのか
期待に応えられなかった人は何が欠けていたのか
![]() 途中でつまづいた人はなぜつまずいたのか など
途中でつまづいた人はなぜつまずいたのか など
さまざまな角度で検証しながら整理しました。
今後も検証を重ねながら精度を上げようと思っておりますが現時点での「たたき台」として参考になれば幸いです。
経営幹部に求められる9つの資質
![]() 人間性・マインド・資質
人間性・マインド・資質
![]() 経営リーダーシップ
経営リーダーシップ
![]() コンセプチュアルスキル(計数能力を含む)
コンセプチュアルスキル(計数能力を含む)
![]() ヒューマンスキル
ヒューマンスキル
![]() 人材育成力
人材育成力
![]() 商売センス
商売センス
![]() 感度
感度
![]() 学ぶ姿勢・開かれた窓
学ぶ姿勢・開かれた窓
![]() 会社へのロイヤルティ
会社へのロイヤルティ
9つそれぞれに詳細項目がありますが、ここでは特にマネージャーに比して、経営幹部により強く求められる2項目
![]() 人間性・マインド・資質
人間性・マインド・資質
![]() 経営リーダーシップ
経営リーダーシップ
これらについてお伝えします。
経営幹部により強く求められる2つ

2つの項目、「人間性・マインド・資質」と「経営リーダーシップ」について、その詳細を一覧にしてみました。
人間性・マインド・資質
- 利他思考
- 他人への感謝の気持ち
- 部下がついていきたくなる人柄
(上だけを見ない、自ら行動で示す、面倒見がよい、気遣い、明るい、ユーモア、人間味 など) - ポジティブ思考
- 素直さ、聞く耳
- 率直で裏表がない
- 多様性の受容、特定の集団だけを優遇したりしない
- 知性、教養
- 倫理観、コンプライアンスの姿勢
- お金に綺麗
経営リーダーシップ
- Will、情熱、結果へのこだわり
- 先見性、視座の高さ
- 想いを伝え相手に影響力を及ぼす力、ストーリーテリング
- 言葉のチョイス、物事をシンプルに表現する力
- 自分独自の考え、意見がある
- 決断力、スピード
- 厳しさ、高い要望
- 度量
- 持続性、粘り、しつこさ
- 変化を恐れぬ勇気と柔軟性
- 未知に飛び込むチャレンジ精神
- 率先垂範の行動力、突破力
- 最後の砦となる責任感、胆力
一覧の活用
上記の一覧は、ぜひ自社の文脈でアレンジし、幹部登用時の選考基準としてご活用ください。
あなたの会社の業態、歴史、企業文化、社長の考え方などを踏まえた独自の「β版基準」として運用を始め、現場で試行錯誤しながら育てていくことをおすすめします。
このような基準が完成したら、それを将来の幹部候補生にもぜひ共有していただきたいと思います。
意欲ある社員なら、自分なりに一覧と照らし合わせながら、自己課題を設定し、日々意識していくのではないでしょうか。
また、組織的に幹部候補生の人材開発をするのであれば、一覧をベースに、各項目に対して「上司による第三者評価」と「本人の自己評価」を行い、それを対比させながら振り返る場があるといいですね。
本人の気づきが非常に大きいと思います。
なぜなら、上記の一覧に書かれている項目は、見ての通り、できていなくても普段他人から指摘されにくいものだからです。
「本人は全く自覚していないのに、周囲は気づいている」なんてことも生じがちです。
だからこそ、第三者からのフィードバックや、自分自身で改めて振り返りを行うことに、とても意味があると思います。
まとめ
経営幹部の登用にあたっては、「経営幹部としての資質」を明確に見極めることが欠かせません。
特に重要なのが マネージャー → 経営幹部 の間に存在する断絶を正しく認識することです。
経営幹部人材の適性は、業務遂行力やマネジメントスキルだけでは判断できません。
なぜなら、マネージャー時代よりも内面的な資質(人間性やリーダーシップ、マインドの高さなど)が強く求められるからです。
この違いを理解していないと、人選の判断がぶれたり、登用後に期待とのギャップが生じたりするリスクが高まります。
今回ご紹介した「経営幹部に求められる資質の一覧」を、経営幹部登用時の判断基準を考えるきっかけとして活用してみてください。
マネージャー本人がこの違いを早い段階で理解していれば、自身の課題に気づき、その差を意識的に埋めていくことも可能になります。
組織全体で「経営幹部とはどのような人材か?」に対する共通認識を持つことが、強い経営チームづくりの第一歩となるでしょう。
こちらの記事もおすすめです。















