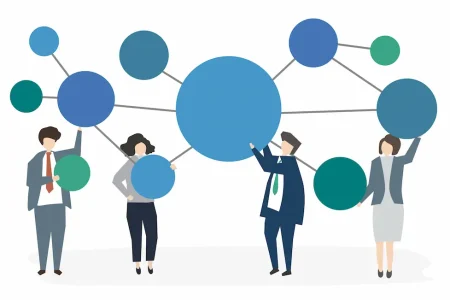「 タバコミュニケーション 」という言葉は、オフィスの喫煙所におけるコミュニケーションのことを意味します。
オフィスの喫煙所で立ち話をしていると、本音が垣間見えたり、会議室では出ない意見交換がなされ、これが結果としていい気づきやアイディアにつながることがあります。
こうした会話は社員間のつながり、特に部署の垣根を超えたつながりを強める効果もあり、経営学者の中にもその効能を説く人がいます。
一方で、煙草を吸わない人が疎外感を感じていたり
![]() 「喫煙所こそが本音で話す場!」
「喫煙所こそが本音で話す場!」
という勘違いをする人も出てくるので、適切に活用しなければマイナス面が大きくなってしまいます。
今週のブログでは、喫煙所でのコミュニケーション「タバコミュニケ―ション」や飲ミュニケーションの是非について考えてみたいと思います。
目次
タバコミュニケーション のメリット

喫煙所は、執務スペースとは切り離された空間にあり、たまたまその時間に喫煙所に来た人同士で会話が発生します。
そのため、以下のようなメリットを創出してくれます。
- 普段会話しない人と会話できる(→社内のつながりが広がる)
- 執務スペースとは違う会話が生まれる(→新たな気づきや発想につながる)
- 職場の上下関係が持ち込まれにくい(→フラットな会話がされやすい)
- 一息つく休憩時間なので本音が出やすい(→現場の実情や他者の本音がわかる)
- 他部署の話が聞ける(→社内の動きを知ることができる)
このように、喫煙所は自由な発言が許容されやすいオフサイト的な空間であり、タバコミュニケーションには多くのメリットがあるのです。
タバコミュニケーション のデメリット

一方で次のようなデメリットも生じます。
![]() タバコを吸わない人は上記のメリットを享受できず、疎外感を感じる
タバコを吸わない人は上記のメリットを享受できず、疎外感を感じる
![]() 喫煙所で何となく意思決定や判断がされると、その場にいない人との情報格差が生じる
喫煙所で何となく意思決定や判断がされると、その場にいない人との情報格差が生じる
![]() 上司が喫煙者である場合、同じく喫煙者の部下とのコミュニケーションに偏り、煙草を吸わない部下が距離を感じてしまう
上司が喫煙者である場合、同じく喫煙者の部下とのコミュニケーションに偏り、煙草を吸わない部下が距離を感じてしまう
![]() タバコミュニケーションが過大評価されすぎると、会議等の公の場で言うべきことを言わず、喫煙所のコミュニケーションで対処しようとする人が出てくる
タバコミュニケーションが過大評価されすぎると、会議等の公の場で言うべきことを言わず、喫煙所のコミュニケーションで対処しようとする人が出てくる
→ 結果として、日中の会議や打合せの場で率直に意見を言い合う風土が形成されにくくなる
![]() 行き過ぎた会社だと、幹部に喫煙者が多い場合、喫煙者ばかりが出世するなどという全く笑えない事態が生じる
行き過ぎた会社だと、幹部に喫煙者が多い場合、喫煙者ばかりが出世するなどという全く笑えない事態が生じる
喫煙所での本音の会話、フランクなコミュニケーションは何ら否定するものではありませんが、そこで交わされた重要な情報は非喫煙者にも共有する必要があります。
また、タバコミュニケーションはあくまで補助的な交流の場であり、日常の仕事の中でこそ皆が交流し、フランクに話せるような風土を作ることも大切です。
喫煙所での会話は、「日常のコミュニケーションに+αを生み出す」程度がちょうどよい状態であり、タバコミュニケーションを過度に重視するようになるとそれは逆効果になります。
今の時代は煙草を吸う人も減っています。
喫煙者はどちらかと言うと女性よりも男性が多い傾向がありますが、職場では女性の比率がどんどん高まっています。
そのため、喫煙所を情報交換の場として機能させることが、公平性の観点からも再考されるべき時期に来ていると言えるでしょう。
飲ミュニケーションの是非

以前ある会社で、幹部同士の飲み会がやたらと盛んで、その場で色んな意思決定がされていく光景を見ました。
お酒が入っているので活発に意見が交わされ、部下も上司に意見を言いやすい雰囲気もあり、フラットな良い議論ができていました。
その場で色んなことが決まり、スピード感もありました。
しかし、しばらくしてから飲み会の場で決まった内容がどうなっているかをチェックしたところ、多くの問題が浮かび上がりました。
飲み会の場の意思決定であるため、どうしても勢いに頼る部分があり、精緻なデータや曖昧な点の確認が不十分になりがちです。
意思決定の質が高いとは言えませんでした。
実行段階での2つの課題
意思決定されたことを実践する上でも2つの課題が見えてきました。
![]() 飲み会の意思決定では実行に移す細部の設計が議論されていない
飲み会の意思決定では実行に移す細部の設計が議論されていない
飲み会の場では、ホワイトボードに書き出したり、細かく議事録をとる人もいません。
そのため、その場の議論は大方針+α程度にとどまり、実行における担当者の割り振り、スケジュールなどが曖昧なままでした。
![]() 飲み会で決めた時の勢いが、翌日職場でシラフになるとトーンダウンしている
飲み会で決めた時の勢いが、翌日職場でシラフになるとトーンダウンしている
本来ならば、飲み会の場にいた幹部は決定した内容を関係する部下に伝え、巻き込み、その気にさせて動いてもらうステップが必要です。
しかしそのフォローアップの熱意がトーンダウンしてしまうため、結果として人を動かせず、実行フェーズでの動きが鈍くなってしまいました。
また、部下からしても、「また飲み会で決まったことか・・・」と軽視される傾向があり、やはり実行力の低下につながっていました。
以上の点から、飲み会の場にはメリットがあるものの、飲み会が力を持ちすぎるとデメリットが多くなります。
お酒を酌み交わしながら、ざっくばらんに意見を言い合い、お互いのコミュニケーションを深めることは有意義ですが、
大事な意思決定は日中の会議や打合せの場でしっかり議論し、具体的な設計まで進めるのが望ましい形です。
飲ミュニケーションも、タバコミュニケーション同様、あくまで「日常のコミュニケーションに+α」を生み出す程度がちょうどよい状態ではないでしょうか。
「 タバコミュニケーション 」や「飲ミュニケーション」に依存しない場づくり
社内のコミュニケーションは公式の場と非公式の場の双方で成り立っています。
いずれも組織活性化に必要ですが、タバコミュニケーションや飲ミュニケーションは非公式であり、かつ参加者が限定されるものであるため、あまり依存することができない手段です。
両者の良いところは活かしつつ、それに頼らない誰でも参加できる場が必要ということがわかります。
かつて自動車メーカーのHONDAでは、「ワイガヤ部屋」が有名でした。
役員同士が同じフロア―の同じスペースに並んで座り、いつもワイワイガヤガヤ色んな話をしていたというものです。
日中のオフィスの場で、皆がフランクに意見を言い合える職場風土を作っていたのだと思います。
会議のような公式の場とは別に、皆で雑談をしたり、何かのテーマで議論し合ったりできる場があることは、企業の風通しを良くし、コミュニケーションの質を高めます。
今後はそのような場を、意図的にどのように作っていくかが問われています。
具体的な方法について、次回のブログで触れたいと思います。お楽しみに!
こちらの記事もおすすめです。