2023年の年始のニュースで興味深い話題がありました。 専門スキル
- ジョブ型雇用を段階的に導入した三菱ケミカルさんは、主要ポストを社内公募に切り替え、これまでに約2,700のポストを公募しました。
ところが、応募があったのは半分で、実際ポストに就いたのは3分の1程度。
結果として、応募がない部署は従来型の会社主導の人事異動で埋めたそうです。
- 同じくジョブ型雇用を導入している日立製作所さんも同様の結果でした。
21年度に約480件のポストを公募したところ、グループの人材が就いたのは3割で、残りは外部からの中途採用だったそうです。
この2つのニュースは、これからの時代における人事異動の難しさを象徴しています。
会社としては環境の変化に応じて必要なポストに自在に人員を配置したいので、公募に積極的に応募して欲しいし、会社主導の人事異動も実施したい。
一方で、社員は自分の専門性を磨き「転職しても通用する力」を身につけたいので、希望しない職種への異動は避けたい。
つまり、会社の人材配置ニーズと社員の希望職種が嚙み合いません。
今後、この問題はあらゆる会社で発生する可能性が高いです。
今週のブログでは、働き手が専門スキル志向の時代において、会社としての人事異動をいかにマネジメントすべきかについてお伝えします。
目次
専門スキル を追求する時代

さまざまな環境要因により、働き手が「専門スキル」を重視する時代へと加速しています。
逆戻りすることはもはやなさそうです。
専門スキル が追求される要因
【働き手側】
- 生涯1社という選択肢が現実味を失い、人生において何度か転職するのが普通という感覚になっている
- 転職できるよう(+給料を上げられるよう)自分の専門スキルを磨く必要に迫られ、会社の判断で部署がコロコロ変わるのを望まない
【会社側】
- 環境変化に適応しながら、必要ポストに機動的に人員を配置、充足したい
- それぞれの職種に求められる専門性が高まったため、部署をまたがる人事異動が減少傾向。専門性の高いポストでは、社内異動よりも経験者の中途採用を優先する場合も多い
- 社員の離職が増えるにつれ、採用した人材に時間をかけて教育しても投資が無駄になる可能性があるため、内部育成よりも社外からの確保に比重をかけやすい
この流れに対して、あなたの会社はどのような対応を考えていますか?
専門スキル 志向の時代 2つの方向性

会社の辞令に従って適宜異動する仕組みにはメリットもありました。
会社に長くいる事を前提に、頻繁な異動命令も受け入れ、その場その場で全力投球してくれる人材は会社にとって貴重な存在でした。
多様な職種経験を通じて全社を深く理解し、幹部育成にもつながりました。
今後の人材マネジメントにおいて、大きく2つの方向性になると考えられます。
欧米のジョブ型に近い方向性
職種をまたがる人事異動は稀で、足りないポストは社内公募か外部調達で補充します。
それを機動的にできる採用競争力を磨きます。
不要となったポストの人材を雇い続ける余裕はないので、その人材が退職して別の会社で活躍できるような流れをつくります。
ただし1社単体の努力だけでは実現が難しい面もあり、日本の労働市場全体がこの方向に動いていかないと矛盾を抱えたままの状態が続きます。
職種を超えた人事異動を継続する
必要なポストを中途採用だけで埋めるのは難しい会社も多いので、社内異動で充足する方法を残します。
しかし働き手は従来型の会社主導の人事異動を望まない時代なので、そこに対応する人事異動の型を作り上げる必要があります。
この問題を解決し、働き手も会社も納得できる人事異動を実現する方法として「社内二刀流」を提案します。
「社内二刀流」のキャリア形成
「社内二刀流」とは、社内にいながら2つの領域でプロフェッショナルな専門性を磨くやり方です。
例えばこのような二刀流が考えられます。
生産管理のプロであると同時に、データサイエンスのプロ
営業のプロであると同時に、人事(特に人材育成や採用等)のプロ
経理のプロであると同時に、法務のプロ
商品開発のプロであると同時に、マーケティングや広報のプロ
まず1つの領域で一定のレベルに到達したら、異動や業務変更を通じて2つめの領域でも技を磨きます。
その後、2つの領域をいったりきたりするもよし、2つの領域を兼務するもよし。
双方の専門性を継続的に高めていきます。
社員は受け身ではなく、主体的に自分がどの領域で専門性を高めるか真剣に考え、上司や人事と擦り合わせします。
会社としては、当該社員を2つの領域以外に異動させることは、本人が望まない限り基本的に行いません。
この社内二刀流方式には、会社と社員の双方にとってメリットがあります。
専門スキル 時代 社内二刀流のメリット
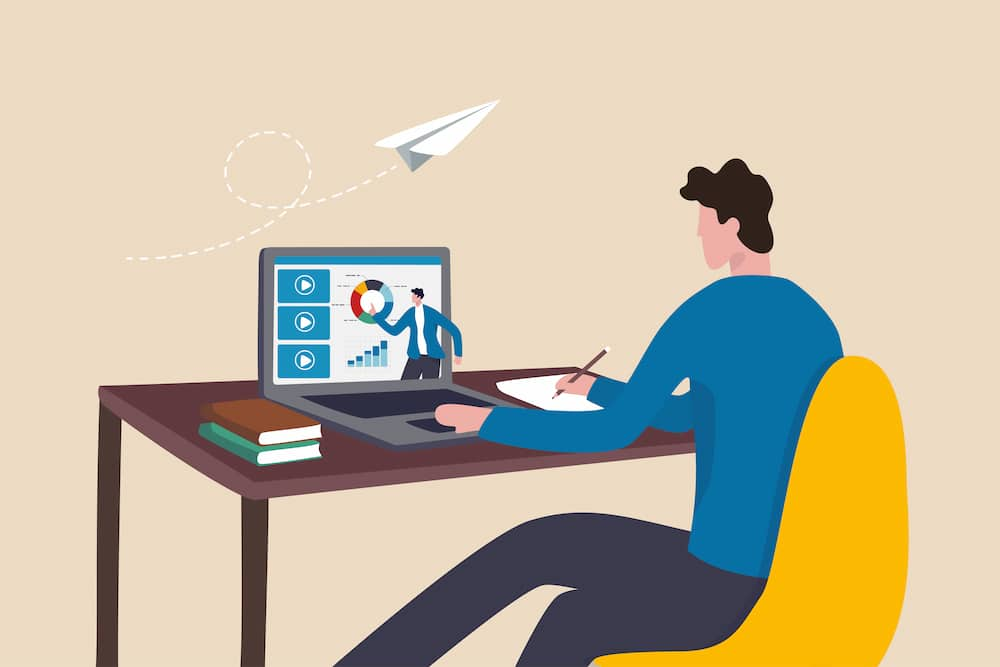
会社側のメリット
■ 専門性の高い人材を育成することができる。社員のマインドとしても「自分の専門性を打ち立てなければならない」という意識が明確になる。
■ 1つしか専門領域がない社員だと異動させることが難しいが、2領域あるので人事異動の機動性が高まる
■ 2つの領域で専門性を磨くと、掛け算効果により社員のパフォーマンスが更に高まる
社員側のメリット
■ 1社に在籍しながら2つの専門性を磨くことができる
■ 2つの領域で専門性を持つことにより、キャリアの拡がりが確保できる。万が一、片方の領域の価値が失われても、他方の専門領域で勝負することができる
■ 転職する際、2つの専門性をもっているので市場で評価されやすい
以上のような社内二刀流を取り入れることにより、個人が専門性を追求する時代においても、社内異動を併存させやすくなります。
三刀流、四刀流もあっていいと思いますが、中途半端な専門性では市場価値がないので、まずは二刀流をしっかり体得するのがキャリア形成ステップとしては現実的ではないでしょうか。
まとめ
会社が必要なポストに人員を充足するには、社内異動させるか、中途採用するかの2択です。
しかし、会社命令で一方的に社員を人事異動させるのが難しい時代になっています。
転職市場は活発とはいえ、中途採用で適した人材を獲得するのも容易ではありません。
この難しい方程式を成立させる1つのやり方として、「社内二刀流」を取り入れてみてはいかがでしょうか?
社員のキャリア形成と会社の人員配置政策を両立させる1つの方法になるのではないかと思います。
こちらの記事もおすすめです。












