昨今は「 管理職になりたくない 」と思う人が増えており、会社は管理職の成り手不足という問題に悩まされています。
そのように思われてしまう原因の1つは、管理職に対するネガティブなイメージです。
例えば
- 残業代がつかなくなり手取りが下がる
- 部下の管理や評価や相談対応など業務が多すぎる
- 業務の大変さの割に得るものが少ない
- 今の上司がいつも辛そうに仕事をしている など
今週のブログでは、こうしたネガティブなイメージを解消し、管理職の本当の魅力をお伝えします。
これをきっかけに管理職の仕事に自信を持ってチャレンジする気持ちになってもらえたら嬉しいです。
目次
管理職をめぐる誤解
管理職という仕事は誤解されがちです。
管理職の仕事をしている人、またはこれから管理職に挑戦する人は、まず誤解をなくし、管理職の仕事の本当の姿を理解してほしいと思います。
以下、管理職をめぐる典型的な誤解について説明します。
![]() 誤解1 上司(管理職)と部下は上下関係である
誤解1 上司(管理職)と部下は上下関係である
![]() 誤解2 管理職は専門性の低い業務である
誤解2 管理職は専門性の低い業務である
![]() 誤解3 管理職の仕事は負担ばかり多く得るものが少ない
誤解3 管理職の仕事は負担ばかり多く得るものが少ない
![]() 誤解4 担当者として成果を出した人は管理職としても仕事ができる
誤解4 担当者として成果を出した人は管理職としても仕事ができる
![]() 誤解5 管理職は資質のある人にしかできない
誤解5 管理職は資質のある人にしかできない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
誤解1 上司(管理職)と部下は上下関係である

上司と部下という言葉の中に「上」と「下」があるので誤解されやすいですが、上司と部下は決して「上下の関係」ではありません。
![]() 上司の役割
上司の役割
部署全体の目標の設定、仕事の配分、人員の配置、部下の育成や評価などを行、部署としての成果責任を負う
![]() 部下の役割
部下の役割
部署の方針にもとづいて、自分が担当する業務領域において成果を出す責任を負う
このように、上司と部下はあくまで「仕事の役割」が異なるだけであり、本質は「共に成果を出すためのパートナー」です。
もし上司と部下の関係を、“上下”と誤解してしまうと
- 部下の意見が正しくても無理矢理自分の意見を押し通そうとする
- 部下が思うように動いてくれない時にパワハラ的な指導をしてしまう
このような勘違いのマネジメントをすることになってしまいます。
上司、部下、双方がセットになって互いの役割を遂行することにより、部署の成果を出すことができます。
そのチーム分業の中で、より役割が大きく、組織に影響力を与えられるのが管理職の仕事です。
誤解2 管理職は専門性の低い業務である
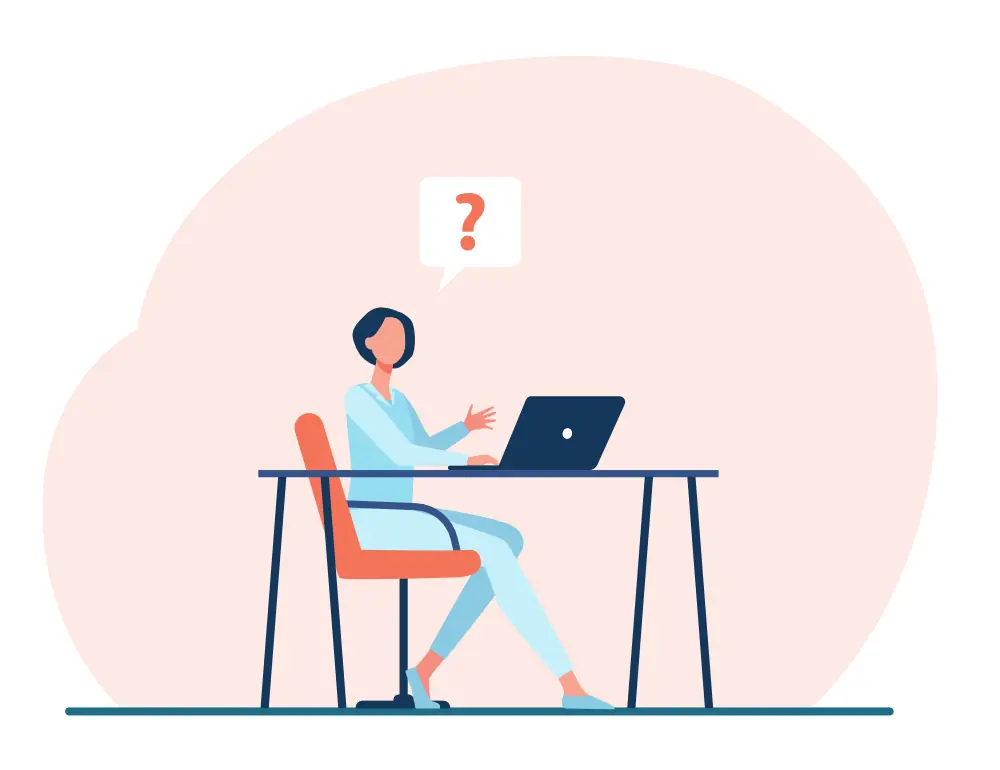
管理職の仕事とはすなわちマネジメントです。
マネジメントは非常に専門性が高く、組織として大きな成果を出すために欠かせない仕事です。
マネジメント力をしっかり身に着ければ、基本的にはどんな会社のどんな部署でも管理職を担うことができます。
「A業界ではマネジメントができるけど、B業界ではできない」というのは、普遍的なマネジメント力が身についていない段階と言えるでしょう。
ピーター・ドラッカーはマネジメントの仕事を以下のように定義しています。
![]() 「目標を設定する」
「目標を設定する」
![]() 「組織する」
「組織する」
![]() 「動機づけとコミュニケーションを図る」
「動機づけとコミュニケーションを図る」
![]() 「評価測定をする」
「評価測定をする」
![]() 「人材を開発する」
「人材を開発する」
ご覧の通り、これらの役割は業界固有の事情に引っ張られるものではなく、普遍的にどこでも通用するスキルです。
管理職の経験は大いに価値があり、将来的に組織を率いていく人、経営を担う人のキャリアステップには不可欠の経験です。
営業のプロがマネジメントも身につければ、「営業×マネジメント」という2つの専門性を持つ貴重な人材になれます。
同様にITエンジニアがマネジメントも身につければ、得難い存在となるのです。
誤解3 管理職の仕事は負担ばかりが多く、得るものが少ない

管理職になると、細々した雑務が増えるイメージがあります。
- 部下の勤怠チェック
- 休暇の承認
- 労務トラブルへの対応
- 問題社員への対応
- 本社から要求される各種書類の提出
- 会社の決め事の部下への伝達 など
このように、成果を出すための本質的な仕事以前の雑務に時間をとられるのは、管理職にとって大きなストレスになります。
一方で、管理職になると担当者時代にはない醍醐味、喜びがあります。
管理職になることで得られるもの
- 経営の一角を担う仕事になり、会社全体の動きが見えるようになる
- 経営陣とも近くなるため、社長が何を考えているか、会社が今どこに向かっているか、会社の課題は何か、などが担当者時代に比べてはるかに見えるようになる
- 関わる社内外の人も一段上のレベルになり、自ずと視座が上がる
- 担当者にできることは限られているが、管理職になればチームメンバー皆の力を結集してより大きなことに取り組める
- 担当者時代にずっと改善したかったことを、組織長になることで推進できる
何より、チーム皆で何かを成し遂げた時に得られる喜びは、担当者時代には決して得られない感動があります。
ネガティブとされることも改善されていく
現在管理職にとってネガティブとされることも、今後は改善の方向に進むでしょう。
雑務
管理職の負担となっている雑務は、徐々に自動化や効率化で負担が減っていく流れにあります。
報酬水準
役割に応じて給与差が開く時代なので、管理職をしっかり担える人の報酬水準は今後さらに上がっていくと考えられます。
管理職の成り手不足から考えても、需要と供給のバランスで管理職の価値は高まります。
以上の流れも見据えると、これからの管理職は決して損な役回りではなく、得られるものが非常に多い仕事と言えます。
誤解4 担当者として成果を出した人は管理職としても仕事ができる

管理職の仕事は担当者業務の延長戦上にはありません。
昇格したからといって、管理職の仕事ができるとは限りません。
担当者時代の経験は役に立つものの、マネジメントについては新たに学ぶ必要があります。
例えば「報告」という業務において、担当者時代と管理職になってからの違いを見てみましょう。
![]() 担当者時代の「報告」業務
担当者時代の「報告」業務
自分の仕事を上司に適宜報告すればOK
![]() 管理職の「報告」業務
管理職の「報告」業務
複数の部下の仕事の報告を受ける立場になります。
そして単に受けるだけでは終わらず、このような業務が加わります。
- 報告の不備の確認、報告書式の決定、次までの宿題の作成、業務のやり方の指導
- 部下から受けた情報をさらに上の上司にレポートする、関係する他部署に横展開する
- 部署の動きや方針などを部下に情報共有/伝達する
このように報告業務1つとっても、担当者時代と管理職時代ではやるべき仕事が異なるので、管理職に求められる仕事が何かを謙虚に学ばなければなりません。
管理職の仕事は、担当者時代のライン業務とは異なる新たな業務であることを理解するのがスタートです。
誤解5 管理職は資質のある人にしかできない

管理職の仕事には特別な資質が必要だと思っている人も多いですが、実はあまり「向き不向き」がありません。
「〇〇さんは管理職向きだよね」と言われるように、担当者時代からその資質を発揮する人もいますが、後からスキルを磨けば誰でも管理職として活躍できます。
よって、入り口で「自分は管理職に向いていないので・・・」と言ってそのチャンスを放棄するのは非常に勿体ないことです。
どのような業界・職種であれ、マネジメント業務で使う能力は主に以下のようなものです。
その1つ1つを高めていけば誰でも質の高いマネジメントに到達可能です。
- コミュニケーション力
- 会議運営スキル
- ファシリテーション力
- チームビルディング力
- 部下指導力
- 業務管理能力(PDCAをしっかり回す)
- 目標設定、計画策定スキル
- ロジカルシンキング
- 人事評価スキル
- フィードバックスキル
- プレゼンテーション力 など
いずれのスキルも、本屋に行けば関連する書籍がたくさん見つかります。
受け放題オンライン研修などののメニューにも含まれているでしょう。
つまり、その気になればいくらでも自分で学ぶことができるスキルばかりです。
大事なのは、学び→実践
学んだことを実際に自分のチームで実践してみます。
そうすると、上手くいったりいかなかったりの経験が蓄積されます。
経験のN数を増やすことで、徐々に自分流のマネジメントスタイルが組みあがっていくでしょう。
マネジメント力は、学び→実践を何度も繰り返すことが肝要です。
我流に陥ることなく、これでいいと満足せず、マネジメントの上手な人を真似して、書籍や研修で学んだことを実践していってください。
マネジメントの上達に終わりはありませんが、怠ることなく工夫改善をしていけば、やがてあなたはマネジメントのプロとしての力を身に着けているはずです。
まとめ

管理職の成り手不足の背景には、現代の働き方や社会的な環境変化が大きく影響しています。
現実に管理職がストレスを抱えながら働いている話を聞くと「そのような働き方をしたくない」と感じてしまうのは無理もありません。
しかしこれらのネガティブなイメージには誤解も多く含まれており、実際は、管理職の仕事には多くの魅力や成長の機会があります。
管理職は組織全体の成果を導くリーダー。
自ら目標を設定し、チームを導き成果を生み出す経験は、他の役職では得られない充実感や達成感をもたらします。
また、管理職の業務を通じて得られるスキルはどの業界でも普遍的に通用します。
管理職の役割をネガティブに捉えるのではなく、むしろ「自分を成長させるための挑戦」として前向きに受け止めることが、自身のキャリアを次のステージへと導く鍵となるでしょう。
こちらの記事もおすすめです。

















