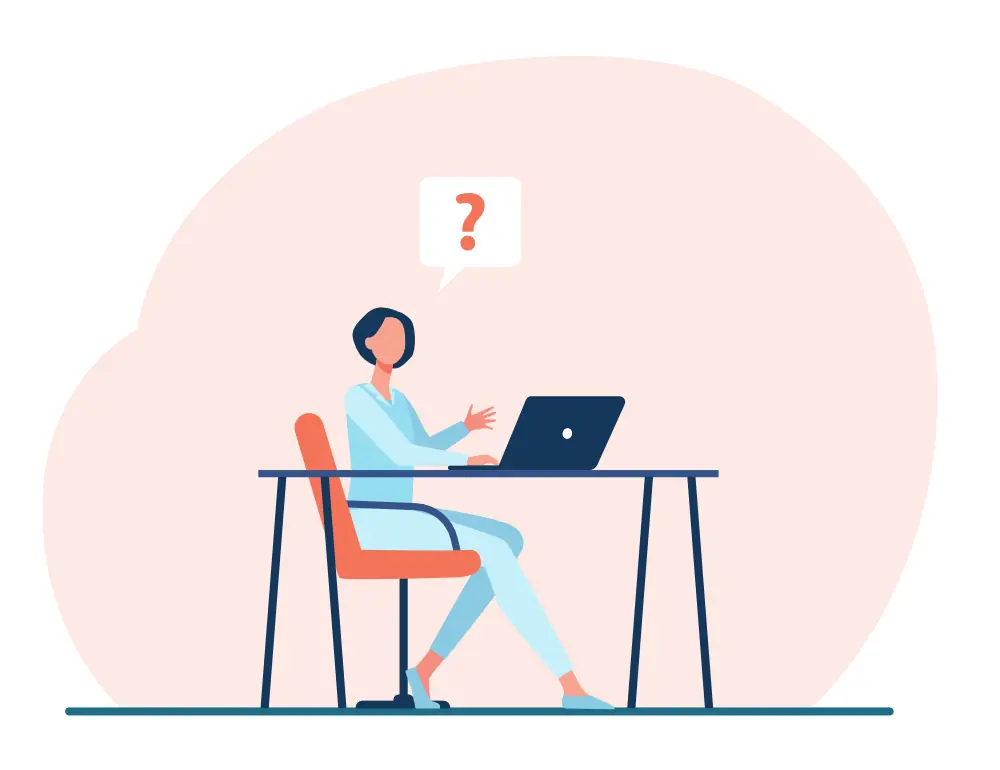思考力
3回シリーズでお送りする「AI全盛時代に向けて備えるべきスキル」の第2回目です。
第1回では、AIを活用するうえで「情報の蓄積=インプット力」がいかに重要かをお伝えしました。
第2回目の今回は、AIを使いこなし、評価し、知恵を引き出すための人間の思考力・概念化力に焦点を当てます。
AIは、膨大な知識を持つ優秀な秘書のような存在です。
そして、その指示役である私たちには「問いを立て、判断し、価値を生み出す力」がこれまで以上に求められるようになっています。
実際にAIと対話した3つの事例をもとに、人間に残された「思考力」の本質を考えていきましょう。
目次
事例1:ロジックツリー作成
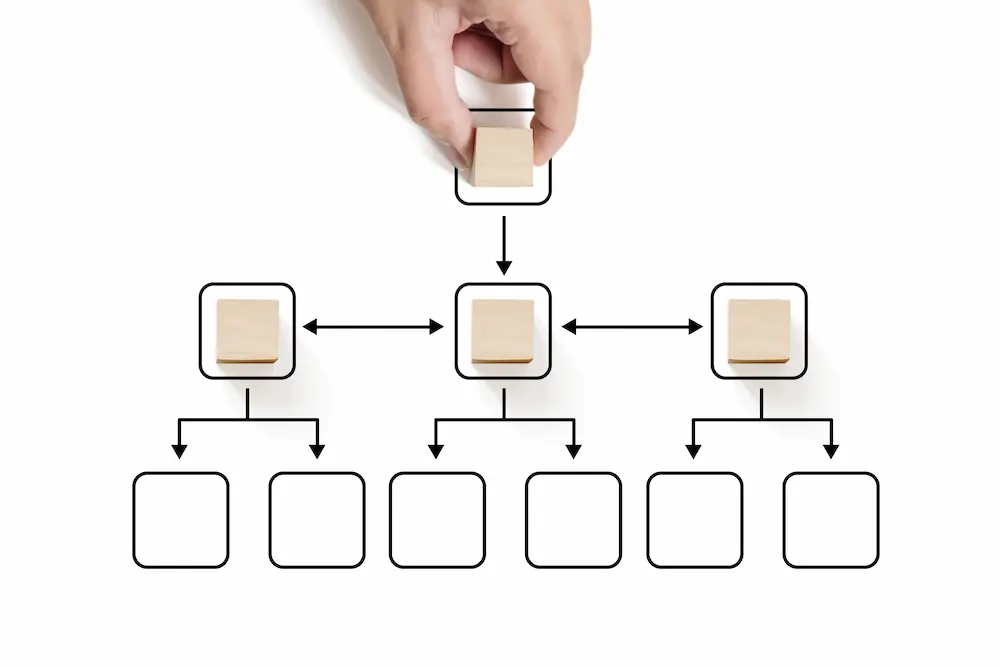
ロジックツリーはロジカルシンキングの基本中の基本です。
その原理を理解するのは簡単ですが、実際に的確に作るのは実に難しいもの。
何度も何度も作って経験を重ねないと、筋が通った構成にはできません。
前回のブログでお伝えしたように、普段からさまざまな話題に関するインプットをしておかないと、ロジックツリーに書くネタ自体も浮かんできません。
今回、実験として生成AIにロジックツリーを作らせてみました。
お題は「日本の少子化の原因」です。
少子化の原因を明らかにすることで「どのような対策をすべきか」を考えられるようにするためのロジックツリーを作成させます。
私自身も以前に取り組んだことのあるテーマですが、ゼロから考えて作るのはなかなか骨の折れる題材です。
以下、生成AIが作成した回答です。
● 結婚する人が減っている
└── 経済的不安(非正規雇用、低収入)
└── 出会いの減少(職場・地域のつながり低下)
└── 結婚に対する価値観の変化(独身志向の増加)
└── キャリア優先(特に女性の高学歴化・就業率上昇)● 結婚しても子どもを持たない(少ない)
└── 経済的負担(教育費・生活費の高さ)
└── 子育ての負担感(ワンオペ育児・育休の取りづらさ)
└── 住環境の課題(保育園不足、住居の狭さ・高さ)
└── ライフスタイルの多様化(DINKs志向)
└── 高齢出産への不安(健康リスク・不妊治療の壁)● 子どもを産みたくても産めない構造的要因
└── 若年人口の減少(出産適齢期人口が少ない)
└── 地方の過疎化(出会いや子育て支援の乏しさ)
└── 社会保障制度への不信(将来不安)
└── 政策の効果が限定的(支援が不十分/使いづらい)
ものの数秒で出してきた回答ですが、さすがです。非常にわかりやすく整理されています。
しかし、これはあくまで第一案。そのままでは使えない理由があります。
【事例1からわかること】
AIの回答を評価・構造化する「思考力」が求められる

AIの作ったロジックツリーはなかなかの出来栄えですが、これを対策議論の材料としてそのまま使うには十分とは言えません。
ロジカルシンキングで習うところのMECE(モレなくダブりなく)になり切っていないからです。
AIの限界は「MECE」と「現実感」
実は、このツリーにはいくつか重要な観点が抜け落ちています。
![]() 日本の経済低迷で一貫して所得が伸び悩んでいる
日本の経済低迷で一貫して所得が伸び悩んでいる
![]() 都市化、一極集中により住宅が狭くなっている
都市化、一極集中により住宅が狭くなっている![]() 都市暮らしで通勤時間が長く、家でゆっくりできる時間が少ない
都市暮らしで通勤時間が長く、家でゆっくりできる時間が少ない
![]() 独身でも十分に暮らしやすい社会になっている
独身でも十分に暮らしやすい社会になっている
![]() 女性の社会進出が進んだ一方、男性の価値観がなかなか変わらず、共働きでも子育て負担は女性側に偏っている
女性の社会進出が進んだ一方、男性の価値観がなかなか変わらず、共働きでも子育て負担は女性側に偏っている
![]() 親世代が孫の面倒を見たり、近所のおじちゃんおばちゃんが時々面倒を見てくれるなどのサポートが減っている
親世代が孫の面倒を見たり、近所のおじちゃんおばちゃんが時々面倒を見てくれるなどのサポートが減っている
![]() 「子供を産む」という生物が本来もっている役割、義務意識が希薄化している
「子供を産む」という生物が本来もっている役割、義務意識が希薄化している
などなど。
生成AIのロジックツリーはなかなかの完成度ではあるものの、色々な角度から考えてみると「足りないな」と感じる点が出てきます。
これらの点をAIに指摘し、ロジックツリーの階層構造などを何度かキャッチボールを経て、以下のロジックツリーが出来上がりました。
少子化の主な原因
● 結婚する人が減っている
└── 経済的な障壁と格差(所得の伸び悩み、非正規雇用、格差拡大、雇用不安)
└── 出会いと支援の希薄化(地域・職場・親族ネットワークの消失、地方衰退)
└── 家族形成に対する価値観の変化
・独身志向、キャリア重視、家族や子孫を持つことの意味の希薄化
・独身でも楽しく便利な暮らし● 子どもを持たない or 一人っ子の世帯が増えている
└── 経済的負担と都市化による生活環境の制約
・教育・住宅・生活コストの高さ
・狭い住環境(都市部の高家賃・持ち家困難)
・通勤ストレス・長時間労働による時間的余裕の欠如
└── 育児負担の集中と社会的支援の不足
・保育・学童・医療体制の不足
・地域・親族の第三者的支援の減少
・男性の育児参画が進みにくい文化(女性に偏る役割)
└── 子育てに対する心理的・社会的障壁
(ワンオペ育児、育児の孤立、自由や趣味との葛藤)● 社会構造と長期的変化
└── 若年人口の減少(出産適齢層の母集団縮小)
└── 社会保障制度への不信(将来不安)
└── 家族観・子孫継承意識の希薄化
└── 豊かさと個人主義の進行(「不便を引き受けない」文化)
だいぶ網羅的に整理されたものになり、これなら対策の議論もしやすくなったと思います。
以上のステップを通じてお伝えしたかったのは、AIにお任せするだけでは求める回答は得られないということです。
AIの活用では、プロンプトの書き方が大事と言われ、「具体的に書く、詳細に書く、・・」などのテクニカルなコツがありますが、それ以上に、そもそも何を伝え、何を問いかけるか?自体がもっと大切です。
AIの出力結果を検証し、妥当であるかを判断・評価するのは人間
生成AIの回答に何が足りないか、論理をどのように整理した方が使いやすくなるか、それを考えるのは人間です。
そうした思考の力・視点の力が加わってこそ、本当の意味でAIを活用できるのだと思います。
生成AIの出現によって、ロジックツリーなどをゼロから考える手間がなくなったのは大変有難いことですが、
AI回答の妥当性を判断するためには、人間が自分でも的確なロジックツリーを作成できる論理的思考力を備えていなければなりません。
思考のフレームワーク(MECE、クリティカルシンキング、なぜ×5回、鳥の目虫の目、原点思考など)を体得する。
さらには、知識や視点の幅も、AIに問いを立てる上で広げておく必要があります。
事例2:ペットの相談

次の質問をAIに投げかけてみました。
![]() 「犬を飼いたいと思っていますが、どのような犬がおすすめですか?」
「犬を飼いたいと思っていますが、どのような犬がおすすめですか?」
賢いAIは早速どんな犬があるかを教えてくれました。
① 忙しい人・共働き家庭におすすめ(お留守番ができる)
トイ・プードル、フレンチ・ブルドッグ
② 初めて犬を飼う人におすすめ(飼いやすい・しつけやすい)
シー・ズー、キャバリア・キングチャールズ・スパニエル
③ 小さな子どもがいる家庭におすすめ(優しい・忍耐強い)
ゴールデン・レトリバー、ラブラドール・レトリバー
④ 小さめで室内飼いに向く犬
チワワ、マルチーズ
⑤ アレルギーが気になる人向け(抜け毛が少ない)
プードル(トイ・ミニチュア・スタンダード)、ビション・フリーゼ
とても優秀な回答ですが、AIが得意とする【大量情報から要約・分類・生成しただけの回答】とも言えます。
もし優秀なカウンセラーが相談者から同じ質問「犬を飼いたいと思っていますが、どのような犬がおすすめですか?」をされたら、どう答えるでしょうか?
恐らくすぐに答えは出さず、逆にこう質問してきたのではないでしょうか?
![]() 「そうなんですね。なぜ、犬を飼いたいと思ったのですか?」
「そうなんですね。なぜ、犬を飼いたいと思ったのですか?」
尋ねた目的、背景を聞くはずです。
「なぜ犬を飼いたいのか?」という問いはオープンクエスチョンで、相手の思考を広げ、話を展開する力があります。
そこで、私はこうAIに伝えました。
私がペットを飼いたいと思った理由は、子供が自立して家の中が少し寂しくなったこと。
無償の愛を注げる対象がいることで心が和らぎ、ストレス緩和になること。
一方で日々忙しいので、飼育の手間はあまりかからない方がいいとも思っている。
そういう意味では、犬がいいのか、猫がいいのか、それとも最近増えている機械の可愛らしいペットもいいのではないかと、迷ってしまう。
するとAIは私の考えに賛同し、犬・猫・ロボットペットの3つについて、ペットを飼う目的に応じた特徴、メリットデメリットを整理してくれました。
これも素晴らしい回答ではありますが、私が提示した3つ「犬・猫・ロボットペット」についてそのまま忠実に回答しただけとも言えます。
もし優秀なカウンセラーであれば、3つに限定せず 「犬、猫以外のペットも考えたことはありますか?」と聞いてくるのではないでしょうか?
選択肢を拡げる視点はAIが苦手とする領域
そこでAIに対して、さらに「犬、猫以外の生き物で、おすすめのペットはありますか?」と質問してみます。
AIはこのように回答しました。
はい、犬・猫以外でも生き物として癒しや心のつながりを感じられるペット、実はいろいろといますよ。
あなたの「愛情を注ぎたい」「でも手間はほどほどに」というお気持ちに合いそうな候補をいくつかご紹介します。
具体的には、うさぎ、小鳥、ハムスター、モルモット、モモンガなどを推奨してくれました。
非常に誠実な回答ですが、これもまた質問されたから答えたという構造になっています。
【事例2からわかること】
AIが苦手とするそもそも論や多角的視点が必要
このやり取りからわかることは、AIは「聞かれなかったことに対して話を拡げ、議論を違う展開にもっていく多角的視点が不得意である」ということです。
よく仕事の議論の場で、手段の話ばかりが進行し
![]() 「そもそもこの仕事の目的って何だっけ?」
「そもそもこの仕事の目的って何だっけ?」
![]() 「私たちはそもそも何を実現したかったんだっけ?」
「私たちはそもそも何を実現したかったんだっけ?」
と、「そもそも論」に戻る瞬間がありますよね。
そもそも論は、仕事で壁にぶつかったときにこそ有効な、非常に重要な思考の切り口ですが、
AIがそれを主導してくれることはありません。
そもそもの目的やゴールを決めるのはどこまで行っても人間だからです。
AIの活用では、人間がただ答えを求めるだけでは浅い答えにとどまります。
![]() 何のためにペットを飼うのか - その仕事の目的は何か?
何のためにペットを飼うのか - その仕事の目的は何か?
![]() そもそも飼うのは生き物? ロボットはなし? - 目的を実現するには当初前提としている解決策でよいのか?
そもそも飼うのは生き物? ロボットはなし? - 目的を実現するには当初前提としている解決策でよいのか?
![]() 犬と猫以外の生き物という解決策はないのか? - 新たな視点にもとづく解決策はないのか?
犬と猫以外の生き物という解決策はないのか? - 新たな視点にもとづく解決策はないのか?
このような問いに自ら立ち返り、AIにない視点を投げかけていく必要があります。
事例3:営業指導の相談

3つ目(最後)のケースは、現場ならではの視点や経験値をAIに伝えながら、よりよい回答を導いていく例を紹介します。
AIは当然ながら、質問者の現場の状況は理解していません。
また、質問者が仕事を通じて体得した勘や経験値を持ち合わせてもいません。
よって、AIの情報整理力と人間の現場視点や経験値を掛け算していく必要があります。
以下、「成績の悪い営業担当者の改善をどうやって行うか?」と質問した際のやり取りです。
![]() 営業成績の良くない社員がいます。
営業成績の良くない社員がいます。
指導してもなかなか改善せず困っていますが、どのように教育したらいいでしょうか?
営業成績の悪い社員への対応は戦略的に取り組む必要があります。
①パフォーマンス低下の原因を見極め、それぞれの対策を考える
A. スキル不足
トークのロールプレイを実施する
優秀社員に同行営業させる
商談後のフィードバックを徹底するB. マインド・意欲の問題
当該社員と面談を行い、気持ちを丁寧にヒアリングする
成功体験を積ませる(小さな目標を設定)
認められる・褒められる機会を意識的に増やすC. 行動量不足
KPIを設定し、進捗を見える化
なぜその行動が必要かの意味づけをしっかり伝える
上司の巻き込み(軽い同行や声がけ)を強化D. 環境・指導者の問題
本人だけの問題ではないことを認識し環境整備を行う
上司や商品開発側と連携して根本改善を模索する
②短期間で変化を促す
また、成績の低い社員はいきなり「自走」はできません。
短期集中育成プランを組みましょう。
回答はバランスの良い、適切な改善アドバイスだと思います。
しかし、現場が分かる実務家の視点に立つと、本当に実効性がある改善策かどうか、いくつか懸念が浮かびます。
![]() 上記の通り指導をやるとなると、上司はかなりの負担です。
上記の通り指導をやるとなると、上司はかなりの負担です。
成績の良くない社員だけのためにそこまで時間を使うべきでしょうか?
![]() しかも、この社員の上司は多忙である上、あまり細やかな指導が得意なタイプではありません。
しかも、この社員の上司は多忙である上、あまり細やかな指導が得意なタイプではありません。
このような状況で、どうすれば現実的な改善につなげられるでしょうか?
AIには現場の実感がない

AIの提案には、対策の優先度や強弱の考えが入っていません。
上司が多忙であることなど実際の状況は、こちらから伝えない限りAIは分かりません。
そこで私は次にこのような質問をしました。
![]() 個別に指導するのはなかなか大変で、上司がかなり時間をとられてしまいます。
個別に指導するのはなかなか大変で、上司がかなり時間をとられてしまいます。
もっと効率的に、仕組みやルールも入れながら、全体の成績を底上げできる方法はありますか?
すると、AIは以下のように回答しました(要約)
はい、「個別に丁寧に指導する」ことと「上司の時間を守る」ことは、仕組み化・ルール化によって両立が可能です。以下のように、仕組みとルールをベースにした育成モデルを導入することで、上司の属人的な関わりを減らしつつ、成果改善を図ることができます。
ステップ1:営業トークスクリプトの標準化
ステップ2:営業日報を「行動+振り返り型」に変更し、考えさせる習慣づけ
ステップ3:週1回の振り返りミーティング(全員同席で相互学習)の実施
ステップ4:行動目標と成果目標の2段階KPI制度で進捗見える化
ステップ5:商談後のセルフチェックシート
この回答は、1~5それぞれ、的を得た改善提言と言えます。
組織全体として1~5を整えていけば、成績の悪い人も普通の人も、業績改善ができるのではないでしょうか。
しかし、やはり実務家としては何かひっかかります。
これまでの経験や勘からすると、ステップ1~5のやり方がまだ十分に具体的ではありません。
これを本当に皆がちゃんと実行するか? 心配です。
やると決めたミーティングが飛ばされてしまったり、日報をすぐにさぼる、などという事態が起きないでしょうか?
そこで、さらに次の質問をしました。
![]() 型やルールを提供しても、成績の良くない人は真面目に型通りやらなかったり、
型やルールを提供しても、成績の良くない人は真面目に型通りやらなかったり、
すぐに諦めて継続できなかったりします。
これをどのように改善させられるかの視点も入れてください。
何度かキャッチボールしてAIが出してきた回答はこちらです。
やること:
① 営業の型を明文化・共通化
トーク例/営業プロセス/ヒアリング質問をマニュアル化し、簡易カードとして携帯させる。使い方研修を実施し、利用を促す。
「型を守っていないと恥ずかしい・指摘される」という仕組みを作る。② 行動と振り返りを日報で仕組み化
「アプローチ数/商談数/型の実行度/反省点」を記録しやすいフォームを作成し、提出を自動化。提出継続者に奨励を出す。③ 週1回の振り返りMTGをルール化
全員で同じフォーマットで振り返り。「良かった商談」「失敗理由」「来週の工夫」などを言語化し、学び合いを促進。主催者持ち回り。④ セルフチェックとロープレを習慣化
商談後のチェックリストや、毎週のロープレを持ち回り当番制に。皆に当事者意識を持たせ、「やらない自由」をなくす仕組みで継続を定着。⑤ “やらない人”には意味づけ+是正指導
型やルールを守らない場合は、「なぜ必要か」をじっくり説明して納得してもらう。回数に応じて是正指導、面談・再配置も検討。
まだまだ細部の詰めや着手の優先順位は必要ですが、従前の提案に比べるとかなり実効性を踏まえた提案になっていると思います。
さて、以上のやり取りを通じて言えることは何でしょうか?
【事例3からわかること】
AIにはない現場視点・経験知が必要

AIは良いアイディアを出してくれるけど、現場のことは分かりません。
対策の実効性には何の責任も負ってくれません。
だからこそ、AIの回答を鵜呑みにしてはいけないのです。
AIにより高い精度で実効性のある対策を考えてもらうためには、人間がAIにどんどん情報を与え、深く考えさせる必要があります。
![]() 現場の状況を教える
現場の状況を教える
(ここでは、「上司が忙しくて成績の悪い社員一人にあまり時間を割けない。個別対応ではなく全体の仕組みで底上げしたい」という現状)
![]() 経験や勘でAIの回答を実践できそうになければ、そう感じる理由を伝える
経験や勘でAIの回答を実践できそうになければ、そう感じる理由を伝える
(ここでは、「ルールを決めたとしても現場が実行・継続できる気がしない」という理由)
このように、よりよいアイディアを出してくれるよう、当方の視点を色々ぶつけながら導く必要があります。
AIはとても賢いですが、質問者の職場、質問者の業務に適したアイディアを出してもらうには、質問者からの情報伝達が不可欠です。
質問者自身が自分の考えをしっかり持ち、仕事の経験蓄積によるナレッジを備え、AIに対して的確に意見表明、情報伝達しなければなりません。
まとめ
以上の3つのケースからお伝えしたかったのは、「AIに任せておけばよい」では不十分だということです。
生成AIは、指示に対して即座にそれらしい答えを返してくれる便利な存在です。
しかし、その答えが「本当に使えるか」「目的に適っているか」を評価し、必要であれば修正を加え、最終的に決めるのは人間の役割です。
AIを最大限に活用するためには、テクニカルにプロンプトの書き方をマスターするだけでは足りず、次のような人間側の力が欠かせません。
1. ロジックを読み解く「理解力」
2. なぜ?を問い直す力=そもそも論を持つ
3. 実行できるレベルに落とし込む「現場視点・経験値」
「人間はAIに仕事を奪われるのではないか?」という声をよく聞きます。
その本質は「思考しない人間がAIに代替される」ということではないでしょうか?
逆に言うと「考える力がある人間」は仕事を奪われることはなく、AIを使いこなす立場になっていくでしょう。
AIに任せられる所はどんどん任せる。
その一方で、AIが出力した情報を、どう咀嚼し、クリティカルに捉え、構造化し、自分なりの答えに変えていくか。
このプロセスこそが、AI時代の人間に求められる力です。
次回はシリーズ第3回。
「人間らしさが価値になる」── AIには代替できないピープルマネジメントの重要性について掘り下げていきます。
どうぞお楽しみに。