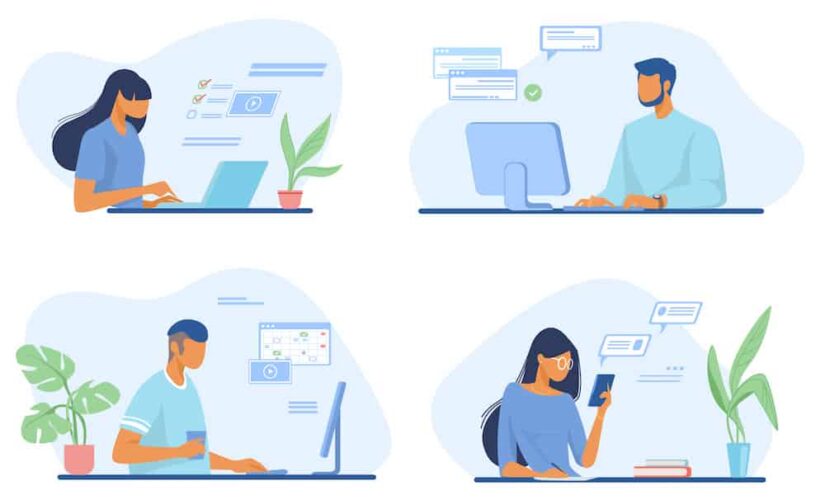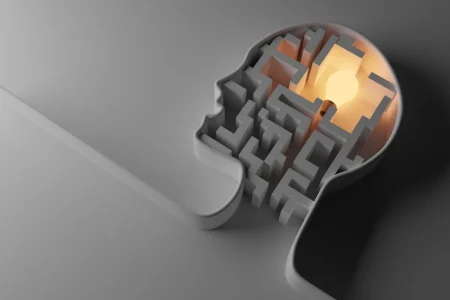近年 リスキリング教育 (Reskilling)の必要性がよく話題になります。
環境の変化が非常に激しく、過去の経験値だけでは時代が求める仕事に適応できなくなっているためです。
危機感を持つ企業はDX研修を用意したり、オンライン教材の会社と提携していつでも動画教材で学べる環境をつくったり、さまざまな工夫をしています。
しかしながら、1つそこに欠けている視点があります。
社員が自ら学ぶ姿勢、学ぶ文化をいかに作り出すか?という視点です。
いくら会社が社員に一生懸命学ぶ環境を用意してあげても、その社員に学ぶ姿勢がなければ意味がありません。
今週のブログは、社員を受け身にさせず、いかに自発的に学ぶ環境をつくるかという内容をお伝えします。
目次
学ぼうとしない社員
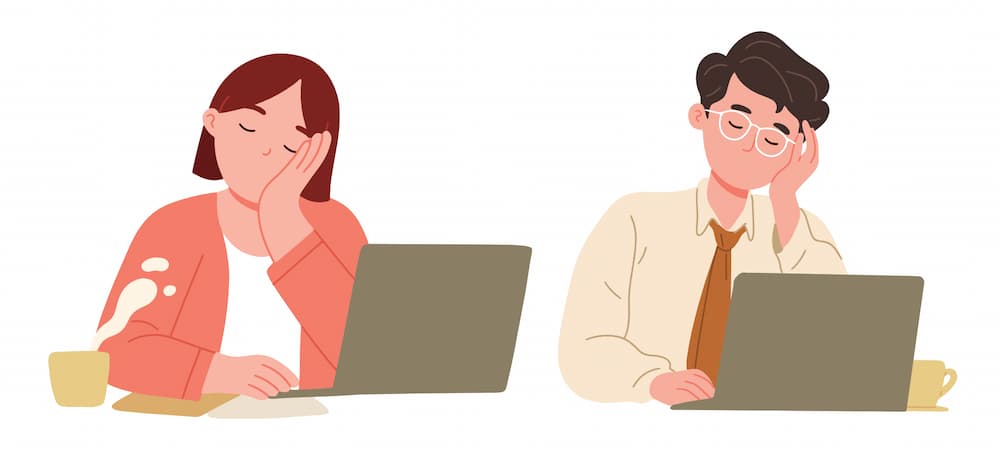
現代のビジネス環境において「学ぶことの重要性」に異論がある人はほとんどいないのではないでしょうか?
ところが、自発的に学んでいるビジネスパーソンは非常に少ないのが実情です。
リクルートワークス研究所が2021年に発表した調査では「会社からの働きかけではなく自主的に学んだ人」の割合はたった26.1%でした。
なんと、4人に3人は自ら学ぼうとしていません。
(2021年7月5日発表「全国就業実態パネル調査」/リクルートワークス研究所)

また同研究所の2018年調査で、「仕事に関連した学びを取らなかった理由」として最も多かったのは、「あてはまるものがみつからない」(51%)でした。
「あてはまるものがみつからない」という理由に受け身の姿勢が象徴されています。
並べられたメニューを見て、自分が学びたいものがあるかを選んでいるだけなのです。
本来ならば、自分のおかれている環境や期待される役割を踏まえて、自ら何を学ぶべきか考え、学び方も考え、主体的に取り組む姿勢が欠かせません。
「自分にぴったりの学びを他人に考えてもらおう」という他人依存にになっている時点で、既に時代に取り残されていると言わざるを得ません。
「勉強=受け身」の考え方→自ら学ぶ姿勢に

日本の教育は子供の頃から宿題と定期考査、そして受験という上から降ってくるイベントに対応しながら勉強を進めるのが基本のスタイルです。
そこに自主性の要素はほとんどどありません。
やるべきことは、与えられた勉強をし、与えられる試験に準備をするだけです。
この結果、「自ら問いを立て、自ら何をどう学ぶか」を考える力が身に付かず、
「勉強=受け身」「勉強=つまらないもの」という感覚が染みついています。
しかしビジネスの学びにおいては、この意識のままでいてもらっては困ります。
なぜなら、全社員に共通する「基礎知識や技能」は、ある程度受け身型の教育や一律の教育で教えることができますが、1人1人の仕事内容や能力/役割に応じた「応用教育」はそうはいきません。
個人間の能力差もあり、役割もキャリアの志向性も異なるので、一律の教育メニューでは限界があります。
かといって、家庭教師のように個々に応じた教育を行なえるでしょうか?
上司が部下1人1人を見ながら個々に応じた育成をすることも重要ですが、それも限界がありますよね。
そこで目指すべき道は、社員1人1人が自ら学ぶ習慣、皆が自発的に学ぶ文化をつくることです。
社員が自発的に学ぶ文化の作り方
会社が与える教育メニューを受け身でこなすだけでは、社員は本当の意味で成長することはできません。
以下は、社員が自発的に学ぶ状態を作るための5つの方法です。
- 仕事の期待値と現状のギャップを伝える
- 学び方を教える
- 学びをシェアする場を用意する
- 目標管理に「学び」を入れる
- 学びとその変化を評価する
一つずつ見ていきましょう。
仕事の期待値と現状のギャップを伝える

出発点は「何を学ぶべきか」を認識することです。
「自分はこれまでの経験だけで十分やっていける!」と思っている限りその人は学ぶ必要性を感じません。
まずは「自分はまだまだ。もっと学ばなければ」と認識させるところからです。
例えばマネジメント経験が10年程度ある営業部のA課長がいます。
本人はマネジメントに自信をもっていますが、実際はとにかくメンバー達に数字のプレッシャーをかけて、結果が出ない人を厳しくつめるというスタイルであるため、社員の定着率が年々悪化しています。
部下の人数が多く本人的には一番大きな部署を統括しているとの自負があるものの、チームの業績も最近は特筆すべきものがありません。
A課長の部下から育った人材もほとんどいません。
このA課長に、次のような期待とギャップを認識してもらいます。
「営業の仕事も仕事もどんどん効率化しており、一方で人材の獲得も難しくなっています。
そこであなたには以下のことを期待します。
- 今の7掛けの人員数で現状同様の売上を確保できるよう人材を育て生産性を高める
- 社員の定着率を●%に高める
- 部下の中から3年以内に係長を●人輩出する
この期待値に向けて自分の足りないことが何かを考えてください」
学び方を教える

多くのビジネスパーソンが自ら学ばない理由の1つに、実は「学び方を知らない」という原因があると思います。
私はよく研修等の場で「どのような方法で自ら学んでいますか?」と尋ねることがありますが、出てくる主な回答は大抵以下の3つです。
- ネットで調べて記事などを読む
- ごくたまに本を読む
- 外部の無料セミナーに参加する
学びの種類がこれだけでは成長に限界があります。
効果的な学び方を、先ほどのA課長の場合で考えてみましょう。
例「部下の能力を引き出すのが苦手なので、コーチングを学びたい」と思った時
情報を集める
①ネット検索して学ぶだけでなく、コーチングに関する本を読む
②少なくともコーチング関連で3冊ほど読み、自分に一番フィットするやり方を書き出してまとめる
③ビジネス雑誌等の部下マネジメントに関する連載を継続して読む
④部下マネジメントに関するメルマガやブログを定期購読する。リーズナブルなオンライン動画コンテンツなども活用する
誰かに教わる
⑤会社の部長クラスや課長クラスでマネジメントに定評がある人に時間をもらって、その人のやり方を教わる
⑥同僚の課長と勉強会などを開き、週に1回集まって、お互いの部下育成の悩みを共有し、いい方法や失敗事例などを学び合う
⑦マネジメントに関して参考になる人をTwitter等で探し、その人とつながる。チャンスがあればDM等で声をかけてみると、運がよければ直接教えてもらえるかもしれない。業界内の会合等で知人を増やし教わるのもあり
⑧部下に自分のマネジメントについてどう思うかを聞き取り(または第三者に聞いてもらう)、問題の本質がどこにあるかを深める

ざっと並べただけでも、学び方にはこれだけの方法があります。
ここでは会社が用意する研修などは含んでおらず、自ら主体的に学べるものばかりです。
①~④の「情報を集める」では工夫している方も多くいますが、良質の情報を仕入れ、仕入れた情報を実際にトライしてみる、やってみて足りないことがあれば更に学ぶというサイクルがポイントです。
無料セミナーなどは何らかの商品を売る前座として講演などが用意されていますが、具体的に役立つ話は滅多にないので、あまりおすすめしません。
⑤~⑧の「誰かに教わる」方法は非常に有効な方法でありながら、あまり活用されていません。
上司や同僚に身近に参考になる事例がたくさんあるのに、そこから学ぼうとしないのは本当に勿体ないことです。
学びをシェアする場(アウトプットの場)を用意する
1人1人が学んだ内容は、互いに発信し合うほど乗数効果が生まれます。
例えば部内のミーティング等の場で、経験知、学びを実践した結果などをシェアすることで、効率よく学ぶことができます。
同僚の話は、本で学ぶよりも遥かにリアリティがあるので、とても身に付きやすいというメリットがあります。
同時に、情報を伝える側にとっては、他者に自分の経験知を伝えるべく頭を整理することで自分自身の学びが深まるというメリットがあります。
下記のような場づくりをぜひ試してみてください。
- 成功事例、失敗事例の事例分析、経験談を共有する
- 自ら学び、実践してみたことの体験談を共有する
- 優秀な先輩の仕事の工夫、学びの仕方などを話してもらう
- 課題図書を決め、そこから学んだことや自分の仕事に生かせることを議論する
互いに学ぶ場が増えるほど、社員は学ぶ大切さを理解し、徐々に「自主的に学ぶ文化」が形成されていきます。
リスキリング教育 目標管理に「学び」を入れる

年度目標や月次目標などを立てる際に、学びに関する目標を入れて、本人の意識を喚起します。
通常の目標管理では、業績目標や業務改善目標を立てますが、並行して、自分は何をどのような方法で学ぶべきかを考え、目標に入れてもらいます。
目標を立てる上では以下のように当面の能力育成と中期的な能力育成と両方の視点から考えてください。
■ 業績目標を達成するために今の自分は何が不足しているか?
■ 今後2~3年後を見据え、自分はどのような学習や能力伸長が必要か?
学びとその変化を評価する
目標管理に学びを入れる以上、業績評価項目にも学びを入れましょう。
■ 自ら何を学ぶべきか考え、実際に学んで習得したかを評価
■ さらにその学びを仕事に活用し、どのように変化したかを評価
学んで終わりとせず、それを実践して自ら変化したかという点を重視します。
半期評価の度にこれを繰り返すことで、自分の学びを意識せざるを得なくなり、徐々に自ら学ぶ行動が増えていくはずです。
リスキリング教育 会社が用意する研修のあり方
冒頭で「会社は社員が学ぶ場を与えるばかりで、社員が自発的に学ぶ環境づくりが弱い」という点にふれました。
学ぶ重要性を理解していないところに研修メニューばかり増やしても、社員はやらされ感が強く、結果として費用対効果に見合うものになりません。
しかし、学ぶ文化ができてくると社員は会社が用意する研修メニューに主体的な意見を持ちます。
「管理職研修にはもっとこういう内容を入れて欲しい」
「営業の顧客コミュニケーションの研修は外部の研修会社依存ではなく、社内の経験知ともとに内製化したい」
このような意見が出てくるようになります。
ここまで来ればかなり理想の状態に近づきます。
社員の自発的な学びと会社の用意する研修が補い合いながら、社員育成を進めていくことができるでしょう。
まとめ

変化の早い今の時代においては、会社が社員に与える教育だけでは追いつきません。
それぞれの職種の細分化、専門化が進んでおり、一人一人が自分に合った学びを繰り返しながら、変化に対応していくことが求められます。
そこで必要なのが、社員が自発的に学ぶ風土を作ること。
そのために5つの方法を試してみてください。
- 仕事の期待値と現状のギャップを伝える
- 学び方を教える
- 学びをシェアする場を用意する
- 目標管理に「学び」を入れる
- 学びとその変化を評価する
とくに②の学び方については理解している人が少ないので、以下の方法などを参考に自分の学ぶ内容にふさわしい学び方を考えてもらってください。
【情報収集】
■ 書籍(少なくとも同テーマで3冊程度)
■ 雑誌の特集など
■ メルマガやブログ
■ 動画教材などのオンラインコンテンツ
■ 研修
■ セミナー
【他人から教わる】
■ 会社の直上司や上層部
■ 会社の同僚(勉強会なども有効)
■ 同業界の知人
■ SNS等で知り合った知人
学んだらそれで終わりではなく、学んだことを必ず実践するところまでで1サイクルです。
さらに学び経験したことを社内の同僚とシェアし合うなど、互いに学ぶ場をつくり、自発的に学ぶ文化を目指していきましょう。
こちらの記事もおすすめです。